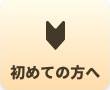健康診断をお勧めするワケとは?
飼い主さんの多くは、動物病院を受診した際や病院からのお知らせで愛犬・愛猫の健康診断の案内を目にしたことがあるのではないでしょうか。
動物病院では飼い主さんが希望すればいつでも健康診断を受けられますし、できれば1年に一回は健康診断を受けておくことをお勧めしています。
どうしてそんなに健康診断を勧めるのでしょうか?
健康診断の最大のメリットは、今現在の体の状態を把握・記録できるということです。
例えば若くて元気な犬猫であっても、検査をしてみたら症状が出ない程度の血液検査値の異常が見つかることがあったり、先天的な疾患が見つかることがあったりします。
つまり病気の早期発見につながるのです。
また、結果的に大きな異常がなかったとしてもその検査記録が残ることに大きな意味があります。
何年後かに病気が見つかった場合、その発症時期がわかりやすくなりますし、病気と関連のある体の変化(体重や尿の性状の変化など)も把握しやすくなります。
例えば心臓病を発症した時にいつから異常が出始めたのか、進行するスピードは速いのか、同時に現れた血液検査の異常値がその病気と関連していそうなのかどうか、などがよりわかりやすくなるなど、様々な利点があります。
愛犬・愛猫が年をとってくると、そろそろ健康状態をチェックしておいてもらおうかな、と考えて来院される飼い主さんが比較的多いですが、元気に見える若い時にも一年に一度は健康診断を受けておくことをお勧めします。

健康診断のタイミング
健康診断を受ける時期は特に決まってはいませんので、ほとんどの病院では希望すればいつでも健康診断を受けることができます。
おススメのタイミングとしては、予防接種などで病院を受診する際です。
犬や猫にとっては病院へ連れていかれるのはあまり嬉しいことではありませんので、病院に行ったときに一緒に検査をしてもらえば、病院に何度も行くことでかかる動物へのストレスを減らしてあげられます。
予防接種の前には簡単な健康チェックをすることがほとんどですので、それと合わせて血液検査などを実施してもらうと良いでしょう。
犬であれば、春~秋にかけて行うフィラリア感染症の予防の前に採血をして感染の有無を調べる機会があると思いますので、その際に少し血液を多くとってもらうと1回の採血で必要な検査と健康診断を両方できます。
特に健康診断をしておいた方がいいケースとしては、新しく犬や猫をお迎えする時です。
環境が変わることで食欲不振や下痢などといった体調不良が起こることがあるのですすが、実は何らかの疾患が隠れているケースもありますので、その可能性を除外するためにも健康診断を受けておくと良いでしょう。
保護猫や保護犬などを先住動物のいる家庭に引き取る場合などは、感染症にかかっている可能性を考慮して、便検査やウイルスチェック、ノミ・ダニ・耳ダニなども付着していないかどうか見てもらうようにしましょう。

健康診断の内容は?
健康診断として実施する項目は動物病院によって多少異なりますが、基本的には以下のような項目をチェックすることが多いでしょう。
・問診
自宅での様子(食欲や元気さ、咳やくしゃみなどの有無、飲水量の変化、その他気になる症状の有無等)を飼い主さんから聴取します
・体重測定
来院時の体重をチェックし、太り気味、標準、痩せ気味などを評価します。
・視診
毛並みや皮膚、怪我などの異常、目や耳、鼻周囲の汚れ、歩き方、動き方などを見て、調子の悪そうなところがないかどうかを見ます。
・触診
体を触ることで、嫌がる・痛がる部分がないかどうか、体表面やお腹の中にしこりなどが触知されないかどうか、関節の動きなどに痛みやぎこちなさがないかどうか、四肢の筋肉の付き具合に左右差がないかどうかなどを見ます。
・聴診
主に胸に聴診器を当て、心臓の音や肺の音に異常がないかどうかを聴きます。先天性の心疾患がある場合、若い時から心雑音が聞こえることがあり、病気の早期発見につながります。
・尿検査
膀胱炎や糖尿病の所見が見られないかどうか、尿中に結晶等ができていないかどうか、尿を作る腎臓の機能に問題がないかどうかなどを検査します。
・便検査
便の色や形状、寄生虫の感染の有無を調べます。
・血液検査
貧血など血液自体に異常がないかどうかを調べる血球計算と、内臓の働きに問題がないかどうかを調べる生化学検査を行い、異常がないかどうかを調べます。
これらの検査で特定の疾患が疑われる場合や、高齢で疾患のリスクが上がっている場合には下記の様な検査を必要に応じて追加します。
・レントゲン検査
胸部や腹部をはじめ、その他異常が疑われる場合には頭頚部や四肢なども撮影します。臓器の形や大きさ、結石の有無、骨の異常などを検出できます。
・ウイルスチェック
猫エイズウイルスや猫白血病ウイルスのチェックなどを行います(血液検査)。初めて検査を受ける場合や感染動物と接触したことが疑われる場合に行います。
・ホルモン検査
甲状腺ホルモンなど、中~高齢期に起こりやすいホルモン分泌の異常を検査します。
・超音波検査
胸部、腹部の臓器の内部構造などを調べます。
・心電図検査
不整脈の有無などを調べます。
・血圧測定
主に高血圧が疑われる場合に検査しますが、病院にいると緊張で血圧が高めになる傾向があるため、あまりルーチンでは行われません。
これらの検査を初めから全て行っても良いですが、検査の費用や動物にかかる負担なども考慮してあげる必要があります。
そのため多くの場合、若い犬猫ではまずは血液検査まで(あるいはレントゲン検査まで)を行い、体に変化が起こりやすい中~高齢期の犬猫ではホルモンチェックや胸腹部のレントゲン、超音波検査などもご提案します。
それらの検査をしたうえで、必要に応じてさらに心電図検査、血圧測定なども加えることがあります。
健康診断としてどの検査がセットになっているかは病院によって異なりますので、事前に電話や受付で費用なども含めて確認しておくと良いでしょう。

健康診断の注意点
健康診断では、様々な情報が得られます。
血液検査では、内臓の働きに問題がないかどうかがわかりますし、尿検査では糖尿病の有無、腎臓の機能、結晶尿の有無などもわかります。
レントゲン検査では内臓の大きさや形に異常がないかどうかや、体内にある結石(胆石、腎結石、膀胱結石など)、加齢に伴う骨の変化などがわかります。
ただし、検査を受けるうえで気を付けなくてはならないこともあります。
まず血液検査について、検査の項目によっては食事の影響によって数値が高めに出てしまう項目があるため、検査当日の絶食が推奨されているものがあるということです。
また尿検査については、採尿してから非常に長い時間が経過したものでは中で菌が増殖して性状が変化してしまったり、結晶が析出しやすくなってしまうことがあります。
尿検査に提出する尿はできるだけ検査当日に採尿し、冷暗所で保管するようにしましょう。
もう一つ頭に入れておいてほしいことがあります。
それは、健康診断でもなかなか検出できない異常もあるということです。
例えば脳や脊髄に生じた異常などの場合は、レントゲン検査や血液検査では検出することが難しく、麻酔をかけてMRI検査などを実施しなければわかりません。
健康診断を受けて大きな異常がないと言われた後でも、神経症状や何かいつもと違う様子が見られた場合には様子を見ず、必ず病院を受診するようにしましょう。

終わりに
健康診断が必要なのは、年をとった動物だけではありません。
先天性の疾患を持っている犬や猫の場合は、若い時の健康診断(聴診や血液検査、レントゲン検査など)で異常が見つかり、そこから精密検査をすることで病気を早期発見することにつながります。
先天性疾患の多くは根治が難しい疾患が多いですが、早期に発見して早めに対処することで将来的にも負担の少ない生活をすることができるでしょう。
そのため、できれば若くても一年に一回は検査を受けて体に異常が起こっていないかどうか見ておきたいところです。
たとえ一度の検査で異常が見られなくても、次の年、また次の年、と検査を重ねていく中で、軽微な血液検査値の上昇などが見つかることもあり、それが病気の早期発見・早期治療につながります。
健康状態をチェックすることで日頃の健康に対する意識も高まり、不調が起こった時にいち早く気づいてあげられるようになりますので、是非、動物病院で相談してみてください。