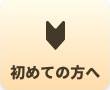換毛期のお手入れ
寒くなってくると犬も猫も寒さに対する体の準備として換毛期がやってきます。
夏の暑さに対応した夏毛が抜け、徐々に寒さに耐えるための冬毛に置き換わります。
換毛期には抜け毛がもつれて毛玉ができやすいため、こまめにブラッシングして抜け毛を取り除いてあげましょう。
毛がたくさん抜けるだけでなく、換毛期には皮膚のトラブルも起こりやすくなります。
もともと皮膚が弱いワンちゃんネコちゃんの場合はフケ、痒み、赤みなどといった皮膚の変化にも気を付けましょう。
寒い時期には服を着せる機会も増えると思いますが、服を着ていると抜け毛が落ちにくく、服の下で毛玉ができたり、服を脱がせたときに自分で毛づくろいをしてたくさんの抜け毛を飲み込んでしまい、毛玉を吐いたり消化管の通過障害を起こす可能性があります。
それらを予防するためにはやはりこまめなブラッシングが大切です。
ブラッシングだけでは追いつかない場合には、一度シャンプーをしてさっぱりさせるのも一つの方法です。
シャンプーの好き嫌いや毛の量、毛質や肌質などによってベストな方法はその子その子によって異なりますので、愛犬・愛猫に合った方法を探してみましょう。

寒さ対策
寒さ対策には暖房をつけるだけでなくいくつか方法がありますので寒さの程度や時期によって様々なグッズを使い分けてみましょう。
① 服を着せる
服は寒さがそれほど厳しくない地域では室内での防寒として、寒さの厳しい地域ではワンちゃんの散歩時の必須アイテムとしても活躍します。
寒い時期に暖房を強くしすぎると部屋が乾燥して呼吸器や皮膚の不調も増えがちですが、ヒトと同じように季節や気候に合った服を着せることで、室温や湿度を適度に保ちながら体温調整を上手にすることができるようになります。
特に、本来は温かい地域で生活する犬猫種(チワワ等)や超短毛種の犬、無毛種の猫、体温調節がうまくできない子犬や子猫、老犬や老猫では寒さへの順応に時間がかかったり、低体温気味になってしまうことがあります。
そんな場合にも服を上手に活用して寒さと付き合いましょう。
② ベッドやブランケット
本格的に寒くなってしまえば一日中暖房をつけることも多くなりますが、寒くなり初めの時期や地域、日によっては暖房をつけるまでもないけれど朝晩は少し冷える、ということもありますよね。
そんな時にあると重宝するのが暖かいベッドや蓄熱性のブランケットなどです。
自分で動ける犬猫であれば、これらを用意してあげれば自分で寒い時に潜り込んで暖をとることができます。
秋冬にはペット用品も寒さ対策に特化したものが多くなり、ペットショップやネットショップでのラインナップも冬仕様に変わりますので、その中で時期や体格に合ったものを選んであげると良いでしょう。
③ ヒーターマットや湯たんぽ
特に冷える夜間だけ、あるいは留守中だけ温めてあげたいという場合にはペット用のヒーターマットや湯たんぽなども活用してみましょう。
ペット用のヒーターマットは高温になりすぎない設計になっているものが多く、専用のカバーなども付属していることがほとんどですのでヤケドの心配もあまりありません。
湯たんぽはお湯を入れる昔ながらのものではなく、電子レンジで温めて長時間保温効果が持続するものが主流ですが、熱すぎないように厚めのタオルで巻いたり、寝たきりの子に使用する場合は少し距離を離して間接的に温めるようにするなど配慮が必要ですので、使い方に気を付けましょう。

乾燥対策
暖房を付けると室内は暖かくなりますが、空気の乾燥が問題になってきます。
寒い季節はただでさえ空気が乾燥しがちですが、暖房をつけると室内の空気はさらに乾燥し、室内の湿度は思ったよりも低くなっています。
そんな環境下では、乾燥による皮膚のトラブルや呼吸器疾患、感染症なども起こりやすくなってしまいますので、加湿をして室内の湿度をある程度のレベルに保つようにしましょう。
ペットが生活する環境の湿度は犬では40~60%、ネコでは50~60%ぐらいが適しています。
ペットだけでなくヒトの健康管理にも効果的ですので、積極的に加湿するようにしましょう。
ただし、近年は加湿器によるトラブルも増えつつあるため、多少注意が必要です。
加湿器にも様々なタイプがありますが、種類によっては加湿器の内部にカビが発生したり、高温の蒸気が出るタイプの加湿器ではヤケドの危険もあります。
ペットが思わぬ健康被害や事故にあわないように使用前に説明書をよく読み、久しぶりに使用する場合にはしっかり清掃するなど機器のメンテナンスや安全管理をよく確認しておきましょう。
皮膚疾患があり、乾燥によって悪化してしまう犬猫の場合、室内の加湿だけでなく保湿剤やクリーム、皮膚の健康維持に役立つサプリメントなどを加えてみることを検討してみるのも良いでしょう。

冬に多い病気への対策
① 呼吸器疾患や感染症
空気が乾燥しやすい寒い時期には気管支炎や喘息などの呼吸器疾患の他、ケンネルコフ、ネコ風邪などと呼ばれるような犬猫の感染症が蔓延したり悪化しやすい傾向があります。
ヒトのインフルエンザが冬季に流行しやすいのと同じで、乾燥した空気中にはウイルスなどが浮遊しやすいためと考えられます。
これらの対策としては、やはり部屋の加湿をして呼吸器の粘膜が乾燥しにくい状態にすること、湿度を保つことでウイルスなどを空気中に浮遊させにくくすることが効果的ですが、もう一つ、予防接種を受けて体に免疫力を付けておくことも重要です。
愛犬・愛猫の予防接種履歴を今一度確認し、接種時期が来ているようであれば忘れずに追加接種しておくようにしましょう。
② 心臓疾患のある動物では…
寒い環境下では血管がギュッと閉まることで体温が低下するのを防ごうとする働きが起こります。
その際の血圧の変化は心臓に負担をかけてしまうため、心臓が悪い犬猫では暖かい部屋から寒い外に出る際などは注意が必要です。
心臓疾患の中でも初期の状態であればそこまで神経質になる必要はありませんが、中程度以上に進行しているような犬猫では室温管理、外出時の防寒、生活環境内であっても部屋ごとの温度差(リビングと廊下、玄関などの差)には注意するようにしましょう。
③ 関節疾患のある動物では…
中~高齢期を迎えた動物では関節疾患を抱える犬猫も増えてきます。
関節に不安を抱える動物では、寒い時期になると筋肉がこわばり関節の動きのぎこちなさや痛みの兆候がいつもより顕著にみられるようになることがあります。
そのような症状があると、お散歩を嫌がる、運動量が減る、筋肉が落ちる、体重が増えてさらに関節に負荷がかかる、というような関節にとってはマイナス要因が増えてしまう悪循環に陥りがちです。
それをできるだけ回避するために、本格的な寒さに突入する前から、お散歩のような負担のかからない運動を継続して行い筋肉量の維持に努め、体重も関節の負担にならないよう適正なレベルに保つようにしておきましょう。
関節部分を冷やさないようにする工夫も効果的です。
季節に合わせて長袖の服を用意したり、不安のある関節にフィットするサポーター等を用意してあげると良いでしょう。
またサプリメントや関節保護成分が配合された食事などで体の内側からケアしてあげることも検討してみてください。
④ 泌尿器疾患のある動物では・・・
秋口から冬の寒い時期には、暖かい~暑い時期に比べて飲水量が落ちるため、尿路疾患が悪化しやすい時期として知られています。
水分摂取量が減ると尿量が減り、必然的に尿の濃さが濃くなってしまいます。
すると尿中に排泄されているミネラル分(リン、カルシウム、マグネシウムなど)の濃度が高くなり、もともと尿中に結晶などができやすい子では結晶が析出しやすくなってしまいます。
その結晶が大きく成長すると結石ができますが、尿道が細くて長いオス猫では結石になる前の結晶であっても尿道に詰まって閉塞を起こしてしまうことがあるのです。
尿道閉塞は発見・処置が遅くなると命に関わることがある緊急事態です。
そうならないためにも、健康診断の一環として普段から尿検査を受け、尿の異常がないかどうかを見ておきましょう。
症状が出る前に結晶尿などが検出できれば、食事管理や水分摂取を促すことで尿の状態を改善することができます。
健康そうに見えていても、寒くなった途端に突然、膀胱炎様の症状が現れることが非常に多くみられますので、しばらく尿検査や健康診断をしていない場合はかかりつけの病院で一度尿検査を受けてみてくださいね。

お散歩時の装備
ネコちゃんの場合はリードを付けてお散歩ができる子は少ないと思いますが、ワンちゃんの多くは毎日あるいは週に何回かはお散歩やお出かけをする機会があると思います。
お散歩は心肺機能の維持や肥満予防、筋肉維持など健康な体を作る上でとても重要な役割を果たしますので、できれば冬になっても続けてほしいところです。
しかし寒くなると、ヒトも動物も外に出るのが少し億劫になりがちですね。
楽しくお散歩するためには快適に外を歩けるように季節に合った服や装備を準備することが欠かせません。
特に、心臓疾患や関節疾患のある子では防寒グッズは必須アイテムです。
体を冷やさない服だけでなく、雨の日や雪の日に活躍する靴や、関節を保護するサポーターなど、便利でおしゃれなアイテムがたくさんありますので、それぞれの愛犬・愛猫に合ったものを楽しみながら選んでみてはいかがでしょうか?
また同時に、一緒にお散歩する飼い主さんも寒さ対策をしっかりするようにしましょう。

気を付けたいトラブル
寒い時期には様々な種類の暖房器具で室温を調節しますが、暖房によるヤケドなどには注意が必要です。
エアコンは温風で部屋を暖めるのであまり問題が起こることはありませんが、ファンヒーターやストーブ、暖炉などを使用しているお宅ではヤケドの危険があるため、予防策を講じるようにしましょう。
特に危険なのはやんちゃで怖いもの知らずな子犬や子猫、また新しく迎えた犬猫などです。
元気に走り回って遊んでいる時や新しく迎えた犬や猫がパニックを起こした際にうっかりストーブにぶつかったり熱くなった金属部分に触れてしまう可能性があります。
またある程度生活環境に慣れた犬猫であっても、ファンヒーターやストーブの真ん前などで長時間同じ部分を熱源に当てて寝てしまう場合は注意が必要です。
温風や熱源に長時間あたっていることで皮膚が乾燥し、ヤケドまでいかなくとも痒みなどの皮膚トラブルに発展してしまうことがある他、程度によっては低温ヤケドによって後になってから皮膚の変色や壊死などといった皮膚障害が現れることがあります。
元気な成犬・成猫であれば暖房との距離などもある程度自分で調節できますが、高齢あるいは麻痺や持病などによって寝たきり状態になっている動物は自力で移動や寝返りができないため、ストーブに近いところで長時間過ごしてしまったり、同じ面をヒーターマットに直に長時間あててしまうことにならないようにこまめに体位変換をしてあげましょう。
蒸気が出るタイプの加湿器でもヤケドの危険性があります。
高温の蒸気が出るものはできれば使用しないか、設置する場所を工夫してペットの手が届かないように配置しましょう。
トラブルを回避するためには、ストーブなどの熱源の周りには柵を設置して近づけないようにすること、寝たきりの動物はこまめに寝返りをさせ、ヒーターマットなどは低温に設定し、直に熱源にあたらないように配慮すること、暖房と共に室内の加湿を心がけ、皮膚の弱い子には皮膚自体に保湿作用のあるクリームなどを塗るなど保湿ケアをすること、などが対策として挙げられます。
寒い時期にもペットとの暮らしを楽しむためには事前の準備が大切です。
ペットの健康を守りつつぬくぬくと暖かに冬を乗り越えるために、愛犬・愛猫の健康状態をチェックしてもらい、どんなケアや準備が必要か見直してみましょう。