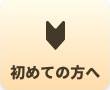ペットたちは一緒にお出かけ?それともお留守番?
飼い主さんが帰省や旅行で長期間出かける場合、まずはペットを一緒に連れて行くのが良いか、ペットホテル等に預ける、あるいは自宅でのお留守番の方が良いかどうかをよく検討しましょう。
飼い主さんが一緒とはいえ、狭いキャリーケースに閉じ込められたままで長時間移動するというのはペットたちにとっては大きなストレスになります。
特に心臓病などの持病がある場合や、狭いケージに入っていることが苦手な犬猫の場合は、長距離移動によって体調不良を招いてしまう危険性もあります。
また、移動した先の環境もリラックスして過ごせる環境とは限りません。
移動が多少負担になっても一緒に行く方がいいのか、自宅やペットホテルでお世話をしてもらう方がいいのか、ペットの体調や性格などをよく考えた上で準備を進めていきましょう。

お留守番の場合…
普段からお留守番をすることに慣れている子の場合、短期間(1~2日程度)であれば自宅でのお留守番も可能と考えられます。
ただしペットの健康を害さないように室温は一定に保ち、食事はいつも通り食べられるように信頼のおける知り合いの方やペットシッターさんにお願いする、あるいは自動給餌器などで飼い主さん自身が管理することが大前提です。
排泄も我慢しなくていいように、室内での排泄ができるように環境を整えトレーニングしておきましょう。
毎日お散歩を欠かさないワンちゃんの場合は、やはりペットシッターさんをお願いするのがいいでしょう。
ペットシッターさんや知り合いにお世話を依頼する場合、知らない人が急に自宅に入って来るとパニックになってしまうことが想定されます。
そうならないためにも余裕をもってあらかじめ顔合わせをしておき、お願いしたいお世話内容の打ち合わせや、フードやトイレ、備品の場所、投薬の有無、お散歩時の注意点、緊急時の連絡先やかかりつけの病院などについて申し合わせておくようにしましょう。
お留守番をあまりさせたことがない場合やお世話をお願いできる人が確保できない場合はペットホテルなどに預けることを検討しましょう。
ペットホテルに預ける場合、年末年始は特に込み合うことが予想され、中には休業日である可能性もあります。
できるだけ早めに予約をとり、必要なものを確認してそろえておきましょう。
ペットホテルに預ける際に必要になるものは、予防接種の証明書等と、治療中の病気がある場合は投薬中のお薬、かかりつけの病院の連絡先、普段食べているお食事とおやつなどです。
予防接種を忘れていた、あるいは予防接種の証明書をなくしてしまった場合は、かかりつけの病院で追加接種や再発行をお願いしましょう。

お出かけの場合は交通手段をよく考えましょう。
ペットと一緒に旅行に行く、帰省する、などという場合、まずはどれくらいの距離を移動するかによってどんな交通手段を使うのが良いか、よく考えましょう。
選ぶ基準としては、移動距離、移動時間、持病の有無(心臓病やホルモン疾患等)、動物の性格、その交通手段を経験したことがあるかどうかなどが挙げられます。
ペットの移動にはある程度費用も掛かりますが、費用を安くするためにペットに苦しい思いをさせるのはできれば避けてほしいところです。
移動距離が長い場合、できるだけ短時間で移動できるものが良いと考えられますが、実際にはケースバイケースです。
例えば海を渡る場合、半日~一日程度かかるフェリーなどでの移動よりは数時間で到着する飛行機の方がいいでしょう。
しかしキャリーケースやクレートに長時間入っていることに慣れていないワンちゃん・猫ちゃんの場合、飼い主さんと離れて飛行機の貨物室で大きな音や振動に耐えることができそうかどうかなど、よく検討する必要があります。
また重度の心臓病など持病のある場合、気圧の変化やストレス下で体調が変化する可能性もあるため、動物の状態が確認できない移動手段はあまりお勧めできません。
場合によっては体調を確認しながら休憩も挟める車での移動の方がいいというケースもあるでしょう。
飼い主さんと離れてしまうとひどく興奮してしまうような子の場合も同様です。
ペット個々の性格や体調、交通機関に乗車した経験の有無などを考慮して、愛犬・愛猫にどんな方法があっているのかをよく検討してみてください。
いずれの移動手段であっても共通して言えることは、犬や猫などのペットの移動時には必ずキャリーケースやクレートなどを使用する、ということです。
車の窓から顔を出しているワンちゃんを見かけることもありますが、不意に飛び出してしまって交通事故にあったり、車内にいたとしても、車がぶつかったときやぶつけられた際などにヒトのようにシートベルトで固定されていないために放り出されて命を落としてしまうことがあります。
狭くてかわいそうと感じるかもしれませんが、大切なペットたちの命を守るためですので、キャリーケースやクレートに入れた上で、シートに固定するようにしましょう。
また、当日の体調がすぐれない場合は、予定の変更も検討しましょう。
移動の日程を変更するか、どうしても変更できない場合はかかりつけの病院に相談して病院で預かってもらうことができないかどうかを問い合わせてみることをお勧めします。
自家用車での長距離移動
車での移動に慣れているワンちゃん・ネコちゃんであれば、車にお泊り用品一式を積んで休憩をはさみながら移動するのも一つの手です。
普段使用しているトイレなども持っていけるため、排泄を我慢させなくてよいですし、常に動物の状態を見られるため、何かあった時に臨機応変に対応できるメリットがあります。
飼い主さんと離れると興奮してしまう子や、ずっと吠え続けてしまうような子の場合はむしろ車での移動の方がおすすめです。
また公共交通機関では搭乗・乗車できる動物の大きさにも制限があります。
超大型犬などの場合は車しか移動手段がないということもあるかもしれません。
乗り物酔いしやすいことがわかっている場合や初めての長距離移動の際は、出発の1時間くらい前までに酔い止めを飲ませておきましょう。
酔い止めはペットショップやホームセンターなどで販売されているものもありますが、とても酔いやすい子の場合は動物病院で処方してもらうお薬の方が高い効果が期待できます。
移動中は吐き気を抑えるために食事は控えた方が無難ですが、休憩時に食べるおやつや水分補給できるもの、移動に半日以上かかる場合は食事も持参しましょう。

公共交通機関を利用する際は…
公共交通機関を利用する場合は、盲導犬などの介助犬を除き、動物は専用のキャリーケースやクレートなどに入れて運ぶのがルールです。
全身が完全に収まるキャリーケースに入れ、入り口はしっかり閉じましょう。
また、不意に入り口が開いてしまったときに脱走してしまわないように、ハーネスを装着してリードなども付けておくとさらに安心です。
その他にも交通機関ごとに規約や守ってほしいマナーがありますので、利用する予定の交通機関を調べ、事前にホームページなどで確認しておきましょう。
① 飛行機で移動する際に気を付けたいこと
飛行機でペットを移動させる場合、事前にペットの分も予約するようにしましょう。
その際、搭乗する飛行機の運航会社のホームページを確認し、飛行機に搭乗させることができそうかどうかを再確認しましょう。
犬種や動物種によっては飛行機に搭乗ができないケースもあります。
犬では短頭種(ブルドッグやフレンチブルなど)の搭乗を断られたり、季節によって搭乗できない期間があることもありますので、判然としない場合は直接航空会社に問い合わせてみましょう。
また健康状態や動物の性質(興奮しやすい性格、飼い主さんとはなれるとずっと吠え続けてしまうなど)によっても搭乗を断られるケースがあるようです。
重篤な持病のある場合はかかりつけの獣医さんに飛行機にのせることについて意見を聞いてみましょう。
飛行機内ではペットは基本的に貨物室に移動し、客席に一緒に搭乗することはできません。
搭乗手続きをする際にペットをクレートなどに入れて預け、その後は目的地に到着して貨物室から出てくるまで状態が確認できなくなることを知っておきましょう。
ペットのいる貨物室の温度や湿度、気圧などは客室と同様になる様に管理されているため、冬季間であっても低体温症になったりする心配はないとされています。
ただし、貨物室までの移動の際には外を通って移動することがありますので、気温の変化などにうまく対応できないような体調の動物では注意が必要です。
搭乗中、客室乗務員がペットのお世話をすることはありませんので、排泄や給水は飛行機に乗る前に済ませておきましょう。
また飛行機に乗る時間が長い場合はクレートに給水器などを付けておきましょう。
乗継便がある場合など、一度ペットを休ませて食事や給水を行う必要がある場合は搭乗便の時間を調節するなど事前計画が重要です。
冬期間は雪などの天候によって飛行機が計画通りに運航しない可能性もありますので、臨機応変に対応できるよう準備しておきましょう。
飛行機に搭乗させるのにはリスクも伴いますので、各飛行機会社が掲げているペットの輸送に関する注意事項をよく読み、了承できるかどうかよく検討してみてください。
② フェリーを利用する場合
船での移動は比較的時間がかかることと、船の揺れはヒトでもそうであるように乗り物酔いがひどく現れることがあるため、個人的にはあまりお勧めしません。
ですが、車で海を渡る旅程を計画している場合などは避けられないこともあるかと思います。
船に乗る場合も飛行機と同様、乗下船時はペットを全身が入るケージ等に入れて運ぶよう規約に記載されています。
その他にも予防接種の有無や体調、ペットの種類・大きさ、同伴できるペットの頭数などについて規定がありますので、まずは規約をよく読み、事前に予約をとるようにしましょう。
船の中ではペットはペット専用のスペースで預かってもらうか、ペットと一緒に過ごせる専用の客室に入ることになります。
フェリーによってはドッグランなどの設備がある船もあり、当日の海が穏やかで荒れていなければ、快適に過ごせることも多いようです。
乗船時にはワクチン証明書(犬の場合は狂犬病予防接種証明書も)が必要になることがありますので持参しておきましょう。
③ 列車や新幹線での移動
列車や新幹線に乗る場合も、ペットは動物専用のケースに入れることが求められます。
さらにその大きさ、重さに規定があり、キャリーに入っているペットを持ち込む際には手回り品切符が必要になることがありますので、改札口あるいはみどりの窓口などに立ち寄る必要があります。
キャリーに入ったペットは飼い主さん自身の膝の上や足元、新幹線では荷物置場・特大荷物スペースなどに置くことができますが、列車によって付いていないことがあります。
事前予約も必要ですので注意しましょう。
公共交通機関は様々な方が利用されるため、たとえ座席があいていたとしても衛生面・安全面を考慮して、座席の上に置くことは控えましょう。
ペットカートやスリングは全身が隠れるものであっても鉄道会社各社によって扱いが異なり、蓋ができないトートバッグなどはほとんどの鉄道会社ではNGとなっています。
利用する予定の鉄道に関してもそれぞれのホームページを確認し、乗車可能かどうか、ペットを入れるケージなどの準備は十分かどうかなどよく確認しましょう。
終わりに
普段あまり長距離のお出かけをすることがない犬猫を、多くの人で込み合う中を持ち歩いて移動するのは、動物自身にも飼い主さんにもかなりストレスがかかります。
そのストレスを少しでも緩和するために、自宅では移動用のケージやクレートに自由に入れるようにしておき、お出かけ本番の前に少しずつ慣らしておくようにしましょう。
中で眠ったり食事やおやつをとれる位になってくれると安心です。
年末年始はどんな交通機関であっても混雑が予想されます。
そんな中には動物が苦手な方やアレルギーのある方などもいらっしゃいますので、飼い主としてマナー違反してしまうことがないように、事前によく計画して準備しましょう。