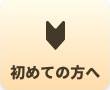肝臓ってどんな臓器?
肝臓は体を健康に保つためにたくさんの働きを担っている働き者の臓器です。
その働きには主に
① 代謝 糖質やたんぱく質、脂質などを代謝する
② 解毒 摂取した薬剤や体内で生成されたアンモニアなどの有害物質を分解・解毒する
③ 貯蔵 グリコーゲンや脂質、タンパク質など栄養素を貯蔵する
④ 分泌 脂質の消化に必要な胆汁を生成し分泌する
⑤ 血液凝固因子を生成する
等があります。
上に挙げた以外にも様々な仕事をしていますが、肝臓は臓器自体が大きく、予備能力が高い上に再生能もあるため、多少の傷害を受けても臨床症状が現れるまでには至らないことも多い臓器です。
そのため、症状が何もないのに健康診断を受けてみたら肝酵素が高くて驚いたという飼い主さんも多いのではないでしょうか。
言い換えれば、臨床症状が現れる時にはすでに肝臓の傷害がある程度進行しているということになります。
沢山の機能を持つ肝臓だからこそ、機能不全に陥るまで病状を進行させてしまうのは避けたいところです。

肝臓病の内訳は様々
一口に「肝臓病」と言っても様々な病態があり、それぞれ全く異なります。
肝臓の病気の原因としては以下のようなものがあります。
・感染症(ウイルスや細菌、真菌、原虫などの感染など)
・慢性肝炎(代謝性、中毒性、感染性、自己免疫性などがあるが多くは原因不明)
・銅蓄積性肝障害(特定の犬種で遺伝性に起こることがある)
・門脈体循環シャント(先天性あるいは後天性)
・肝リピドーシス(主に猫、長期の飢餓状態などに伴っておこる)
・中毒性肝障害
・腫瘍
これらの他にも、胆嚢や十二指腸、膵臓など、隣接する臓器で起こった炎症などが波及して肝臓に障害が起こることもあります。
しかし実際は、はっきりとした診断名がつかずに、軽度の肝酵素の上昇だけが継続するケースも多く見られます。
原因がはっきりしているものに関しては、投薬や必要に応じて手術などが治療の選択肢になりますが、原因がよくわからないままに肝酵素が高いケースの中には、食事内容や与えているおやつの見直しだけで肝数値が下がるものもあります。
様々な栄養素を貯蔵、代謝、合成する肝臓ですので、食事の内容は思ったよりも大きく影響していることがわかります。

肝臓の回復にはある程度のたんぱく質が必要
特別な疾患を除いて、血液検査で肝臓の数値が高めの場合にはバランスの取れた総合栄養食を与えることが勧められます。
「肝臓病用の療法食があるならそっちの方が良いのでは?」と思う方もいらっしゃると思いますが、肝臓病用の療法食の中には、銅が関連した肝臓疾患や、アンモニアの解毒がうまくできない状態になった肝臓病など、比較的重篤な疾患の時に給餌されることを想定されて作られているものもあるため、その適用には注意が必要です。
肝臓病用の療法食を使用してはいけないわけではありませんが、1点だけ注意したい点があります。
それはタンパク質の含有量です。
肝臓病用の療法食の中には、タンパク質の代謝によって生成されるアンモニアを低減することを目的として、低タンパク質の組成になっているものが比較的多くあります。
しかし肝性脳症を起こしている症例以外ではタンパク質を必要以上に制限する必要はなく、むしろ傷害された肝臓の再生にはある程度のタンパク質が必要と言われています。
そのため、肝臓病療法食を与える際にはタンパク質の含有量をチェックし、必要に応じて少し追加してあげなくてはいけないのです。
となると、そもそも肝臓病用の療法食でなくてもいいケースが多々あり、高消化性の高品質なたんぱく質を含む総合栄養食などでの管理の方が適していることも多いのです。
食事療法の必要性については、かかりつけの先生に相談してみましょう。

肝臓病の療法食ってどんなフード?
肝臓病の療法食は数社から販売されていますが、ターゲットとしている疾患が大体同じであるため、以下のような特徴を持っているフードが多くなります。
・タンパク質の量が調整されている(低く設定されている)
・肝臓疾患時に負担となる成分が制限されている(銅やナトリウムなど)
・肝臓の働きを助ける成分が含まれている(BCAA、Lカルニチン、亜鉛など)
1.タンパク質について
肝臓にはタンパク質を代謝するという重要な働きがあります。
消化管で消化されたタンパク質はアミノ酸として吸収されて肝臓に運ばれ、肝臓内で体に必要な様々なタンパク質に再合成されます。
タンパク質を代謝する過程でアンモニアという有害物質が生成されますが、健康な肝臓はそれを解毒する働きも持っているため、通常は問題になりません。
しかし重度の肝障害によって解毒機能が落ちると、高アンモニア血症から肝性脳症という神経症状を起こす状態に陥ることがあります。
そのリスクを回避するために、肝臓病の療法食ではタンパク質を制限してあるものが多いのです。
しかしタンパク質は体の維持や肝臓の再生にも必要となるため、極端に制限しすぎることは良くありません。
リスクを減らしつつも体に必要なタンパク量を確保するために、肝臓疾患の療法食では、消化性の高い良質なタンパク質を調整して配合することで、代謝時の負担を軽減しながら肝臓の再生・回復をサポートしています。
2.負担となる成分について
銅は体に必要な成分ですが、肝臓病の中には銅が肝臓の細胞に蓄積して肝障害を起こす病気があります。
この疾患の場合には、摂取する銅を必要最小限にすることが重要になります。
また肝臓の病気の中には、アルブミンというタンパクの合成が低下するような病気があり、重症になると腹水貯留や体の浮腫を起こしてしまうため、それらの症状を軽減するためにナトリウムの摂取量を制限することがあります。
肝臓病の療法食は、そのような疾患・病態時に与えることを考慮して、これらの含有量を少なくしているものが多く見られます。
3.働きを助ける成分について
肝臓病の療法食には、BCAA、Lカルニチン、亜鉛など肝臓の働きを助ける成分が添加されているものも多く見られます。
BCAAとは分岐鎖アミノ酸であるバリン、ロイシン、イソロイシンの総称です。
肝機能の低下によりアンモニアの代謝ができなくなると、筋肉がBCAAを消費してアンモニアを分解します。
消費されて少なくなったBCAAを補給することでアンモニアの代謝を促すだけでなく、体内のアミノ酸バランスを維持することで体に必要なタンパクの合成や肝臓の再生に必要なタンパクの合成もサポートできます。
Lカルニチンは通常肝臓で合成され、脂肪の代謝やエネルギー産生に必要不可欠な栄養素ですが、肝疾患時にはLカルニチンの生成量が減少してしまいます。
Lカルニチンを補給して脂肪の燃焼・代謝を促すことは、脂質の代謝時にかかる肝臓の負担を減らすことになります。
亜鉛はアンモニアの代謝に関わる補酵素として働く成分です。
通常は小腸で吸収された後、アルブミンというタンパクと結合して肝臓に運ばれますが、肝障害によってアルブミンの合成が低下すると亜鉛は吸収されずに排泄されてしまいます。
そこで、タンパクの原料となるアミノ酸とともに亜鉛を補給してあげることで肝臓の機能をサポートできます。
さらに亜鉛には銅の吸収を妨げ、肝臓を守る働きがあります。
そのため、銅蓄積性肝障害をはじめとする様々な肝臓病で適度に摂取することが推奨されています。

療法食が必要な肝臓疾患
肝臓病の療法食があるということは、特別な配合でつくられた食事が必要な病気があるということです。
それらは比較的多い軽度な肝酵素の上昇ではなく、肝臓の構造や代謝に何らかの異常があるために、本来解毒・排泄できる物質が体に蓄積してしまうような疾患です。
下記のような病気の際には特に肝臓病用の療法食の効果が期待できます。
① 銅関連性肝炎(銅蓄積性肝障害)
銅は体に必要な必須微量元素の一つですが、必要以上に銅が肝臓の細胞に蓄積してしまう疾患があります。
この疾患には好発犬種があり、よく挙げられるのはベドリントンテリア、ラブラドールレトリバー、ダルメシアン、ドーベルマン、ウェストハイランドホワイトテリアなどで、一部では遺伝性の要因も指摘されています。
銅は腸で吸収されたあと、肝臓に運ばれて代謝され、最終的には胆汁に排泄されます。
この代謝経路のどこかが破綻すると肝臓に銅が蓄積し、肝細胞が傷害されて食欲不振や下痢・吐き気などの消化器症状や肝酵素の異常な上昇がみられるようになります。
この病気の確定診断には肝臓の生検(組織の一部をとって検査すること)が必要です。
この病気の好発犬種であり、比較的若い内から異常な肝酵素の上昇がみられる場合にはしっかりと検査を受け、診断してもらうことが必要です。
この病気の時には、銅の摂取量が治療の要になります。
銅の排泄を促す薬剤の投与も行われますが、銅の含有量を低減した食事を与えることでさらなる蓄積を抑制でき、治療がうまく進みます。
この病気の場合、タンパク質の制限はあまり必要ありません。
もし与える療法食の配合が低タンパク質の組成になっている場合は、不足分のタンパク質を添加することが必要になる場合もあります。
② 門脈体循環シャント
門脈は、腸で吸収された栄養成分を肝臓に運ぶ重要な血管です。
門脈があることによって腸で吸収された糖やアミノ酸、種々のビタミンなどの栄養成分が肝臓に運ばれて代謝され、必要に応じて貯蔵されたり解毒されたりして体の健康状態が保たれています。
この門脈が先天性に発達していない、あるいは後天性にうまく機能しなくなることによって、本来肝臓に運ばれて代謝を受けるはずの栄養素や毒素が肝臓を介さずに全身循環に流れてしまうのが門脈体循環シャントという病気です。
この病気の際には、肝臓で代謝されて解毒されるはずのアンモニアが全身循環に流れ込むため、高アンモニア血症による神経症状を呈することがあります。
この病気の根本的な治療は外科的にシャント(短絡)血管を閉鎖し門脈への血流を確保することです。
外科処置をするまでの間や、外科処置がうまくいかない症例、あるいは根本的治療が難しい後天性の門脈シャントの症例などでは、高アンモニア血症になることをできるだけ回避する必要があります。
アンモニアは体内でタンパク質が代謝されると発生するため、この病気の治療中はタンパク質の摂取を必要最低限に抑えた食事を与えます。
また、肝硬変などに伴って高アンモニア血症を起こしている場合も、同様の食事が推奨されます。
③ 肝リピドーシス
肝リピドーシスとは、肝臓の細胞に異常に脂肪が蓄積してしまう病気です。
猫が長期間飢餓状態に陥るとなりやすい病態で、肝酵素が非常に高くなるほか、黄疸や強い吐き気、食欲廃絶などといった深刻な状態になります。
肝リピドーシスの場合は、肝臓病の療法食は特に必要ありません。
むしろ必要なのは高栄養の食事を少量ずつでも摂取させて、肝リピドーシスの状態から一刻も早く脱することです。
食事として使用されることが多いのは、高消化性で高栄養のフードで、患者自身が食べることができない場合はカテーテル(経鼻カテーテルなど)などを介して流動食状にして注入することもあります。

肝臓に負担をかけないために気を付けたいこと
軽度の肝酵素の上昇では特別な療法食よりバランスの取れた高品質の蛋白を含む総合栄養食で十分と書きましたが、それ以外にも日常の食事・健康管理として気を付けたいことがいくつかあります。
まず、フードの消費速度についてです。
ペットフードにはドライタイプ、ウェットタイプ、セミドライタイプなど様々な形状のものがあります。
ウェットタイプのフードはあまり日持ちがしないという認識が浸透しており、開封してから長期間経ったものは与えない飼い主さんの方が多いでしょう。
しかし、ドライフードも開封してからの経過時間や保存方法に注意が必要です。
開封前のドライフードは窒素充填されているため酸化しにくい状態ですが、ひとたび開封すると毎日少しずつ酸化していきます。
そのため、開封してから1カ月以上経った食事は、それだけで肝酵素の上昇を招いてしまうことがあります。
さらに湿気の多い梅雨時などはカビの発生にも注意が必要です。
開封した食事はできるだけ短期間で食べきれるよう、愛犬・愛猫の体格を考慮して小分けのパッケージで販売されているフードを選び、開封した後はできるだけ密閉できる容器に入れ、高温多湿の場所は避けて保存するようにしましょう。
また食事ではなくおやつが原因で肝酵素の上昇を招いてしまうこともあります。
特にジャーキーなどを与えすぎることはあまりお勧めできません。
おやつを漫然と与えることは避け、ご褒美やコミュニケーションツールとして必要最低限の量で上手に使いましょう。
肝臓は予備能力が高い「沈黙の臓器」ですので、初期にはあまり症状を示さないことも多い臓器です。
特に肝臓病の好発犬種とされている品種では定期的に血液検査を受けて早期発見に努め、肝臓の病気のサインを見落とさないように気を付けましょう。