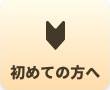犬と猫の心臓病
「心臓病」と一口に言っても、その病態は様々です。
中高齢の犬では僧帽弁閉鎖不全症、猫では肥大型心筋症が比較的多く、その他には特定の犬種で好発しやすい疾患として拡張型心筋症などがよく知られています。
また稀ですが、先天的に心臓の中隔という壁に穴があいていたり、自然に閉鎖して退縮するはずの血管が残っていて血流に支障をきたしてしまうような病気が見つかることもあります。
これらの心臓病は健康診断などの際に偶発的に見つかることもありますが、呼吸の苦しさや運動不耐性など何らかの臨床症状が認められてから見つかることも少なくありません。
偶発的に見つかった無症状のものでは、直ちに治療が必要とはならないこともありますが、心臓病に関連した臨床症状が認められた場合の多くは投薬治療が必要になり、その治療はおそらく生涯続くものとなります。
さらに、心臓病は治療をしていてもわずかずつですが進行して病状が徐々に悪くなるため、必要なお薬の種類や投薬量は増えていく傾向にあり、治療のためにたくさんのお薬を飲ませなくてはならない状況になりがちです。
お薬を飲むのが苦手な犬猫の場合、薬が多いと飲ませられず治療がうまくいかないこともあります。
そんな心臓病治療の中で、お薬以外で心臓病にかかる負担を減らしたり心臓の働きをサポートできる成分を補充できるのが食事療法やサプリメントです。
心臓病の治療薬は血圧や心臓の収縮力などに影響を与えるものが多く、その使用の開始時期は定期的な検査を重ねた上で慎重に見極める必要があります。
一方で食事療法は、血圧を上昇させる要因を取り除いてマイルドに心臓病の負担を軽減してくれるため、取り入れることで悪影響が出ることはあまりありません。
理想的な食事管理ができれば日々心臓にかかる負担を減らすことができ、心臓病の進行スピードを遅くすることにも繋がります。
ここからは心臓病の進行を抑制するためにはどんな食事が適しているのか、心臓の働きをサポートするような成分にはどんなものがあるのかをご紹介したいと思います。
これらを上手に使うことで、心臓病の進行をできるだけ抑制し、病気と上手に付き合っていけることができたらいいですね。

心臓病の悪化要因
心臓病になってしまった場合はどんなことに気をつけたらいいのでしょうか?
心臓に負担をかけやすい要因として高血圧や肥満が挙げられます。
これらを管理・予防することは心臓に過剰な負荷をかけないために重要です。
また、重度の心疾患の場合には「心臓性悪液質」にも注意が必要です。
それぞれについて簡単にご説明していきます。
①高血圧には要注意
高血圧は様々な原因で全身の血管に高い圧力がかかった状態です。
血圧は心臓から拍出される血液の量や、血管の収縮・弾力性の低下などと密接に関わっています。
ヒトでは塩分の過剰摂取や生活習慣病などから生じる動脈硬化が原因で血管が硬くなること、喫煙による血管の収縮などが原因の一つとして挙げられますが、動脈硬化や喫煙は動物の場合はあまり当てはまりません。
塩分の過剰摂取は、ヒトの食べ物を頻繁に食べている、あるいはおやつをたくさんもらっている犬猫では該当する可能性があります。
心当たりがある場合は食事内容を一度見直し、改善しましょう。
その他に、犬猫ではホルモン疾患(甲状腺機能亢進症や副腎皮質機能亢進症)、慢性腎臓病による高血圧など、他の疾患が原因で起こる高血圧が問題となることが多く、心臓病の治療をする際にはこれらの異常が起こっていないかどうかについても併せて検査してもらうことが大切です。
高血圧になると心臓には通常よりも負荷がかかった状態が持続することになりますので、徐々に心筋の収縮力が低下したり、心臓の筋肉の肥大を招いてしまいます。
一度変化の起こった心臓を元に戻すことはできないため、できるだけ負荷をかけないことで心臓が大きくなってしまわないようにすることが重要です。
②肥満は心臓病の大敵
肥満もまた高血圧の原因となります。
体が大きくなると体を動かす際に必要な力が必然的に大きくなるため、その分心臓にかかる負担が大きくなります。
それだけでなく、体が大きい分循環する血液量も多くなるため、心臓にかかる負担は思ったよりも大きいのです。
肥満は様々な病気の発症リスク・悪化要因でもありますので、できるだけ適正体重をキープできるように食事管理を行いましょう。
③心臓性悪液質とは?
悪液質とは重度の全身疾患などによって栄養不良状態が生じて衰弱した状態をいいます。
重度の心臓病の場合にも悪液質に陥ってしまうことがあり、体の筋肉や脂肪が減少して体重の低下が見られます。
悪液質に一度陥ってしまうと、通常の食事管理による栄養サポートでは回復することが難しく、食欲は低下し活動性も落ちるため、進行性に衰弱していきます。
筋肉の減少は骨格筋だけでなく心臓にも認められることがあり、それが心機能をさらに低下させることになるため、予後不良となってしまいます。
そのため、悪液質に陥らないように早めに対策しておくことが重要です。

心臓病の患者さんに適した食事とは?
心臓病の患者さんでは、高血圧や肥満などにならないように気を付ける必要があります。
そのため、心臓病の療法食として作られたフードには、下記のような特徴がみられることが多くなります。
・Na量を制限している
・体重管理しやすい組成
・必要なタンパク質やカロリーを確保しやすい組成
・心臓の働きをサポートする成分を含んでいる
① ナトリウムの制限
ナトリウムは体内の水分量の調整に関わる成分です。
ナトリウムをたくさん摂取すると血管内の水分量が増え、その結果、循環血液量が増えて高血圧になりやすくなります。
高血圧の状態が長く続くと心臓に常に負担がかかることになるため、心臓病の管理のためにはナトリウムを過剰に摂取しないようにすることが大切です。
ヒトの心臓病では塩分の摂取量に気を付けるように言われますが、塩分に含まれるNaの過剰摂取が問題となるためです。
ペットフードでも心臓病の療法食ではナトリウムを過剰に摂取しないように制限してあるのが一般的です。
② 肥満の予防
肥満の予防もとても重要です。
健康な犬猫でも、肥満を予防することは様々な病気の発症リスクを下げることにつながりますが、心臓病の場合は特に体重管理が大きな意味を持ちます。
肥満傾向になり体が大きくなると、体を循環する血液量が増え、それを全身に送り出す心臓にも常に負担がかかった状態になります。
さらに、体重が増えることで体を動かすときにかかる負担が大きくなるため、ちょっとした運動で呼吸が苦しくなったりすることが多くなり、運動を控えざるをえない状態に陥りやすくなります。
そうなると運動不足によってさらに体重が増えやすくなり、それによって心臓にはさらに負担がかかるという悪循環に陥ってしまうのです。
心臓病になってしまってからダイエットをする場合、運動で負荷をかけることは避けたいところですので、やはり食事管理が重要になってきます。
ただし筋肉量はできるだけ落とさずに体重を落とすことが必要ですので、脂肪分があまり多くなく、良質なたんぱく質が適度に含まれた食事で筋肉量を維持しながら少しずつ減量できるような食事を選びましょう。
③ 悪液質に陥らないために
心臓性の悪液質に陥ってしまうと、そこからのリカバリーは非常に難しいものになります。
そのため、悪液質に陥らせないような食事管理が重要です。
悪液質を予防するためには、十分なカロリーを食事から摂取すること、消化吸収しやすい良質なたんぱく質を十分摂取することが必要です。
そのため、食欲が低下しがちな高齢犬でもしっかりカロリーが取れるような高栄養の食事や適切にタンパク質を含む食事などが推奨されます。
ただし高栄養の食事と言っても肥満傾向にさせてしまってはいけません。
また、心臓病と併発することが多い慢性腎臓病に罹患している犬猫では、高タンパクの食事が病態を悪化させてしまう可能性もあるため、タンパク質の量を低めに設定しているフードの方が適している場合もあります。
体がやせてきている場合には栄養価の高い食事を、肥満傾向であれば体重管理がしやすい食事を、腎臓病も治療中の場合はタンパク質やリンなどを制限した食事を、というように個々の状態に合わせて食事選びをする必要があります。
食事の選択については、気兼ねせずかかりつけの病院で相談して一緒に選んでもらうことをお勧めします。

心臓の働きをサポートする成分
心臓病の療法食や心臓病用に作られたサプリメントには、心臓病の治療薬ほど劇的に効果がみられるわけではありませんが、日々の心臓の働きをサポートしてくれるような成分が含まれています。
その代表的なものをいくつかご紹介します。
① Lカルニチン
Lカルニチンはアミノ酸の一種で、心臓の活動と脂肪燃焼に欠かせない栄養素です。
骨格筋や心筋に存在し、脂肪を代謝してエネルギーを作り、血中のコレステロールや中性脂肪を下げるとともに心臓のリズムを整える働きもあります。
脂肪を燃焼することで肥満のリスクを下げ、結果的に心臓にかかる負担を軽減することに繋がります。
本来は肝臓や腎臓でつくられる成分ですが、年齢と共にその量が減少することがわかっているため、加齢に伴って起こる心臓の機能低下を予防するためには食事やサプリメントで適度にLカルニチンを補給してあげることが有効と考えられます。
② タウリン
タウリンもアミノ酸の一種で、心臓の筋肉に多く存在し、血液を全身に送り出す心臓の働きをサポートしている栄養素です。
猫はタウリンを体内で合成することができないため、食事で補う必要があり、猫にとっては特に大切な栄養素といえます。
現在のように良質なペットフードが普及する前は、タウリンが添加されていないあるいは不足している食事を食べていた犬猫でタウリン欠乏が起こることが多く、それによって拡張型心筋症の発症が多く見られました。
しかし今ではタウリンの重要性が認識され、ほとんどのペットフードにタウリンが添加されるようになり、心臓病用に作られた療法食ではさらに強化して配合されるようになりました。
③ DHAやEPA
DHAやEPAは魚油に含まれる不飽和脂肪酸という成分です。
体にとって様々な良い効果が謳われていますが、心臓病に対しても血液をサラサラにして循環を良くする効果や、血管の炎症などを抑制することで血管の健康を保つ効果があり、人医療では動脈硬化の予防効果がよく知られています。
血管の健康を保つことは高血圧の予防になり、心臓の負担を軽減することにも繋がると考えられます。
④ 抗酸化成分
抗酸化成分には様々なものがありますが、中でもよく知られるビタミンCやビタミンEも添加されていることが多い成分です。
これらは血管の酸化を防ぐことで血管を健康に保ち、心臓からの循環を保つことで心臓の健康を守る働きをしてくれます。
これらを適切な量で含む食事は、心臓の健康を守りながら働きをサポートでき、心臓病のリスクを減らし、進行予防にも役立ちます。

食事療法はいつから始めるべき?
心臓病の食事療法は、心臓に何らかの異常が認められたら早期から始めることが勧められます。
早期から食事で負担を軽減することで、将来的に重症化するリスクを少しでも下げることができると考えられます。
ただし、初期の心臓病の場合は必ずしも療法食として販売されるフードでなくてもよい場合があります。
総合栄養食として販売されているフードの中にも、良質なたんぱく質を使用し、Naが適度に制限されているフードがありますので、それらを維持食として上手に活用してみましょう。
低ナトリウム、低リン、低たんぱくでありながら高栄養の組成となっているウィズペティの「毎日美食」なども、初期の心臓病や腎臓病を併発している心臓病のワンちゃんにおすすめです。
また、他の疾患を治療中の場合はその病気の治療との兼ね合いもありますので、かかりつけの獣医師に食事療法を始めてもいいかどうか、どんな食事を選択すべきかどうか相談してみましょう。

終わりに
もし愛犬・愛猫の心臓に異常を指摘されたら、心臓以外の全身の状態も一度しっかり検査してもらいましょう。
心臓病と同時に起こりやすい中高齢期の疾患の一つに腎臓病があります。
心臓と腎臓は血圧調整に関わるホルモンの分泌をそれぞれ行っているため、その病態は関連していることが多く、腎臓病によって高血圧となり、それが心臓に負担をかけて心臓病の症状を発症するケースもあります。
体の問題は心臓だけなのか、他に関連している病気がないかどうかを初めからしっかり調べてもらうことで、正しい治療ができ、正しい食事管理につながります。
心臓に病気があっても適切な治療を行えば、長く元気で過ごせるケースはたくさんあります。
いつまでも笑顔で一緒にいられるように、食事の選択も上手にしてあげたいものですね。