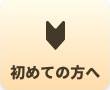認知症とは?
認知症(認知機能症候群、高齢期認知機能不全などともいう)とは、高齢期に認知機能が徐々に低下していき、複数の特徴的な行動障害を示すようになる症候群です。
加齢による脳の萎縮や機能の低下によって、それまで日常的に行ってきた生活動作がうまくできなくなり、しつけを忘れてしまったり、性格が変化したり、無目的な吠えや徘徊などといった様々な症状がみられます。
人医療分野では発症のメカニズムや治療方法などが研究され、各種検査に基づいてアルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症、血管性認知症などといった分類もされており、近年は初期の認知症患者の治療薬が開発されてきています。
しかし犬や猫の認知症の発症メカニズムの詳細はまだ不明な部分が多く、ヒトのような病型の分類はされていません。
ヒトのアルツハイマーの病態と類似するのではないかと考えられてきましたが、細胞に起こる変化が異なっていたり、脳細胞の変化が認知症の発症と本当に関連しているのかどうかは不明瞭な部分が多く、犬や猫とヒトの認知症の発症メカニズムは全く同じではない可能性が示唆されています。
柴犬などは認知症の好発犬種としてもよく知られており、また、目が見えなくなる、耳が遠くなることで外部からの視覚的・聴覚的な刺激が減少することや、歯を失うことによる噛む刺激の減少、てんかんなどの神経症状を示す持病の有無、寝たきりになること、運動不足などは認知症の発症リスクを上げる要因として考えられています。

認知症の特徴的な症状
認知症の症状としてよく見られるものを以下に挙げます。
・ボーっとしていることが増える
・飼い主さんや周りの物事に無関心になる
・無目的に歩き回る(徘徊)
・同じ場所でくるくる回る
・家の中で迷う
・部屋の角や狭いところに入り込んで抜け出せなくなる。
・昼と夜が逆転する
・排泄を失敗する
・しつけ(コマンド)を忘れる
・無目的に鳴く、吠える
・性格が変わる
・不安行動が増える
これらに加え、視覚などの感覚機能が低下したり、ふらつきや転倒、頭を下げて歩く、小刻みに震えるなど、歩行や姿勢の異常を併発することもあります。
これらのうちのどの症状がみられるかは症例ごとに異なりますが、多くの場合はこのうちの2つ以上の複数の症状が現れ、進行とともにその数や症状の強さが増加していきます。
これらの症状は脳や神経に重大な病気を抱えている場合や、加齢とともに増えるホルモン疾患・内臓疾患の場合、歩行に異常を起こす可能性のある関節疾患などでも見られることがあるため、それらの病気と鑑別診断をすることはとても重要です。
鑑別のためには、一般的に全身状態を把握するための血液検査・ホルモン検査、尿検査などが行われ、必要に応じてレントゲン、超音波検査なども行います。
脳腫瘍や脳炎、水頭症など脳や神経の病気を疑う場合にはMRI検査などが可能な二次診療施設などへの受診を提案されることもあります。
ただしMRI検査をするためには全身麻酔が必要となり、検査できる施設が限られ、費用も高額になってしまいます。
必要に応じて行われるのが一般的で、年齢や全身状態を加味して認知症が濃厚に疑われる場合には必ずしも行われる検査ではありません。
認知症の場合、症状は時間の経過とともに緩やかですが徐々に進行していきます。
特に問題となるのは、昼夜の逆転と無目的な鳴き(吠え)で、集合住宅などに住んでいる場合にはその声が近隣からのクレームにつながることも多く、飼い主さんの精神的なストレスにもなりがちです。
そのため、認知症であることが疑われた場合にはできるだけ進行させないように早期から積極的に対策していくことをお勧めします。

認知症に対してできる治療
現段階で認知症を「治す」治療方法はありません。
人医療では初期のアルツハイマー病の患者さんに有効とされる治療薬が開発され、実際に治療も開始されたようですが、その適用は限られているのと、現段階では治療費がとてつもなく高額になることが報じられています。
将来的にはそのようなお薬が獣医療分野でも活躍する日が来るかもしれませんが、まだまだ遠い先の話になりそうです。
動物の認知症に対してできる治療としては、認知症に伴って現れている症状を緩和する治療と、認知症の進行をできるだけ抑える治療となります。
認知症で現れている症状に対する治療としては、大きく分けると以下のようなお薬が使用されることがあります。
・認知症の症状全般に対する治療
・昼夜の逆転を改善する治療
・寝つきを良くする治療
・不安感を軽減する治療
認知症の症状全般に対する治療では、脳の神経伝達物質を増やす作用のある塩酸セレギリンやドネペジル、脳の血流を良くすることで脳循環を改善する作用のあるニセルゴリンやプロペントフィリンといったお薬が使用されることがあります。
これらのお薬はそれぞれどんな症状に対して効果が出やすいかが異なり、症状の組み合わせによっては投薬が好ましくないケースがあると考えられます。
またドネペジルは動物薬として使用承認されていないほか、プロペントフィリンは国内では入手できず、塩酸セレギリンは後述する抗不安薬をはじめとする精神作用のある他のお薬との併用は禁忌でその他にも様々なお薬との飲み合わせに注意を要するため、投薬の開始についてはかかりつけの獣医さんとよく相談することが重要です。
決して飼い主さん独自の判断で投薬を始めたり、急に投薬をやめたりしないようにしましょう。
k
昼夜が逆転して夜間の不眠がみられる場合は、昼と夜のメリハリをつけ体内時計を調整するために、朝日を浴びる、日中は日光浴をする、夜は電気を消して眠りを誘発するなど環境面での配慮をしたり、後述するサプリメントやメラトニンという睡眠に関わるホルモン剤を補充して症状の緩和を目指します。
これらの治療を行っても改善せず、夜間にひどく鳴くことが問題となってしまう場合は、鎮静作用のあるお薬を使用することで睡眠を誘発することを検討します。
認知症によって不安行動が強く出てしまう場合、例えば飼い主さんがいなくなると激しく鳴く、物音や知らない人を怖がり過剰反応してしまうような場合は、抗不安薬や抗うつ薬などで症状が緩和するかどうかを見ます。
お薬の効果の出方は個体差があり、お薬の組み合わせ、投薬量や投薬方法についてはかかりつけの獣医さんと密に連絡を取り、よく相談することが必要です。

認知症を進行させないために…
認知症の進行を遅らせるためには、食事やサプリメントで脳の機能維持に有効とされる成分を積極的に摂取すること、お散歩などの適度な運動を継続すること、脳を使った遊びを取り入れること(脳トレ)なども有効とされています。
① 食事
食事は大前提として年齢に合った食事を選ぶことが基本です。
認知症を発症するのは高齢期ですので、ベースとしてシニア用の総合栄養食を選びましょう。
その上で抗酸化物質や脳に良い成分を含む栄養バランスの整った良質なフードを選ぶことを意識しましょう。
シニア用のフードの中には、脳の健康維持のためにオメガ3脂肪酸が添加されていたり、エイジングケアのために抗酸化成分などが強化されているものが多くなっていますので、そのような食事を選んであげると良いでしょう。
ただし、基礎疾患がある場合、食事療法が必要な疾患を治療している場合、肥満傾向であると指摘されている場合等には、そちらを優先してフードを選ぶ必要がありますので、かかりつけの病院で相談して決めるようにしましょう。
② サプリメント
サプリメントは必ず摂らなければいけないものではありませんが、特に積極的に摂取させてあげたい成分を補充するのに便利です。
認知症の進行予防におすすめの成分は、認知機能の改善が期待されるDHA、EPAや、脳細胞の酸化傷害を防ぐために抗酸化物質であるビタミン類(ビタミンA、ビタミンC、ビタミンEなど)、コエンザイムQ10、ポリフェノール類(フェルラ酸、フラボノイドなど)などが代表的ですが、その他にも様々な成分が認知機能の低下予防に役立つとされています。
以下に認知症に対応したサプリメントに含まれる代表的な成分とその効果をご紹介します。
・DHA、EPA:オメガ3脂肪酸の一種で、青魚に豊富に含まれています。神経細胞の発育や神経伝達物質量を増やすことで脳を活性化して機能維持に重要な役割を果たしています。また血管や赤血球の細胞膜を柔らかくして健康に保つことで、血流を改善する効果があります。
・抗酸化ビタミン類(ビタミンA、ビタミンC、ビタミンEなど):脳は代謝が活発で大量の酸素を消費するため、活性酸素がたくさん発生します。活性酸素は細胞や組織にダメージを与え、加齢に伴う病気の発生に関与しています。ビタミンEやビタミンCなどのビタミンをはじめとする抗酸化成分は、活性酸素を除去するのに役立ち、脳細胞のさらなるダメージを減らしてくれる作用があります。
・コエンザイムQ10:強い抗酸化作用を持ち活性酸素を抑えながら、抗酸化ビタミンであるビタミンEの働きを助けます。
・フェルラ酸:玄米や米ぬかに含まれる天然ポリフェノールの一種です。
脳神経の健康を維持する働きがあり、加齢に伴い蓄積する脳のダメージを軽減し、DHAやEPAが働きやすいようにサポートしてくれる効果も期待できます。
・イチョウ葉エキス:血管の健康を維持しつつ血管を拡張して血行促進に役立つフラボノイドや、強力な抗酸化力によって脳細胞を活性酸素から守るギンコランなどを含みます。また人のアルツハイマー型認知症の原因物質であるアミロイドβタンパクの蓄積を妨げる働きもあるとされています。
・亜麻仁油:アマの種子から抽出された油で、オメガ3脂肪酸の一種であるα-リノレン酸を豊富に含みます。α-リノレン酸はEPAあるいはDHAに変化して脳の栄養素として働き、脳機能を活性化してくれます。
・GABA:アミノ酸の一種で神経伝達物質として働きます。ストレスを軽減したり興奮を抑える効果があります。認知症の動物の中には不安感が強くなってしまうケースもあるため、GABAをとることでリラックスさせ不安傾向を軽減させる効果が期待できます。また興奮状態を抑え、睡眠に入りやすくしてくれる効果もあります。
ウィズペティのサプリメント「毎日一緒 DHA・EPA」は上記の様な脳機能の維持に役立つ成分をバランスよく含んだサプリメントです。
認知症の犬猫の治療の大きなサポートになってくれる可能性がありますので、ぜひお試しください。
③ 知育遊び・運動
認知症になってしまっても、可能であればお散歩の習慣は続けるようにしましょう。
適度な運動は筋肉を維持して自分の足で歩ける期間を長く保つ上で重要ですし、外で風を感じたりいろいろな臭いを嗅ぐこと、車の音をきいたり土や草を踏む感触、他のワンちゃんとの触れ合いなど、適度に様々な外界からの刺激を受けることは認知症進行の予防に役立ちます。
自宅からあまり出ない子では、知育玩具で遊ばせたり、おやつを隠して探索させたり、飼い主さん自身がおもちゃで誘って遊ぶことで適度に運動させてあげるのも効果的です。
動物がワクワクするような適度な刺激を与えながら運動することは脳を活性化させ、認知機能の維持につながります。
同じような観点から、日光浴をすること、マッサージをしてあげることなども心地よい刺激を与え脳の活性化につながりますので、ぜひ取り入れてみてください。

認知症のケアをするときにしておきたいこと
認知症になると、以前はなかったような行動がみられるようになり、それらによって怪我をしたり命に関わる状態になる場合もありますので、生活環境を見直しあらかじめ対策しておきましょう。
徘徊がみられるワンちゃん、猫ちゃんの場合、普段は入り込まないような場所に入って出られなくなったり、階段やベランダから転落してしまう危険があります。
無目的に歩くようになってしまった場合は危険な場所には入れないようにゲートを設置したり、行動範囲をある程度制限できるようにサークルを設置したりすることを検討しましょう。
サークル内にご飯やお水、トイレなどをセットしてあげることで、歩行の異常が症状として現れている場合にもアクセスしやすくなります。
必要に応じて食器を少し高さのある台に置いてあげ、トイレの容器は縁の段差が高くないものにしてあげると入りやすくなり、排泄の失敗回数が減ることがあります。
ペットが過ごす場所は人の出入りが多くて落ち着かない場所や外の大きな音が響くような場所は避け、静かにゆっくり過ごせる場所を選ぶようにしましょう。
やんちゃな同居猫・犬がいる場合や家庭内に小さなお子さんがいる場合には、その過剰な干渉を避けられるように配慮してあげると良いでしょう。
排泄の失敗は症状の進行とともに高率に現れます。
失敗してもある程度場所が決まっている場合や、寝ている間の失禁の場合は、あらかじめペットシーツを敷いておけば飼い主さんの負担も少なくて済みます。
いつどこで排泄してしまうかわからない場合は、動物にとっては少し不快かもしれませんがオムツの装着も検討しましょう。
認知症によって不安症状が強く出ている場合には、生活スペースに犬や猫のフェロモン剤などをスプレーしたり拡散させることでリラックス効果を高め、症状を軽減できるかもしれません。
このようにペット達が過ごす環境を整えることは、犬猫自身だけでなく飼い主さんの負担を軽減することにもなります。
時には数年にわたってケアが必要になることもありますので、症状や愛犬・愛猫の体の状態に合わせて快適に過ごせる工夫を模索してみましょう。

認知症になってしまった愛犬・愛猫と長く付き合っていくために
ペット達が認知症になってしまったとき、そのお世話は「介護」の要素が強くなります。
排泄のケアや自力で食事がとれない場合には食事の介助、寝たきりになってしまった場合には定期的な体位変換、加えて昼夜を問わない吠えへの対応等、症状によっては誰かが常に近くにいてお世話にあたらなければならない状況になります。
そのため、お仕事をされている飼い主さんがお仕事を休んだり、勤務形態を変えることを余儀なくされることもあります。
大きな声で鳴いたり吠えたりしているのをどうやっても制御できず、ご近所からのクレームが来るようになってしまうと、飼い主さんもさらに精神的に追い詰められてしまい、長年連れ添った愛犬・愛猫なのにお世話をするのが辛い…、そんな風に思ってしまうことがあるのも仕方ない状況になってしまうこともあります。
そんな時は一人で抱え込まず、積極的に病院で相談しましょう。
「治す」治療方法はありませんが、症状を緩和する方法はいくつかあります。
それだけでなく、誰かにその悩みを聞いてもらうこと、いろいろな経験を積んでいる病院のスタッフに共感してもらい一緒に考えてもらうことで、心の負担や疲れがかなり楽になります。
場合によっては、一時的に預かりをしてもらうことができれば飼い主さんの休息時間も作れます。
長寿と呼ばれるまで元気で頑張ってくれている愛犬・愛猫を最期に悔いなく見送れるよう、日々できることを模索し、ペットたちが安心して過ごせるようなケアを目指しましょう。