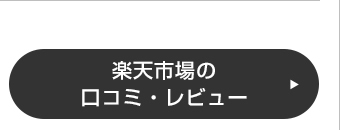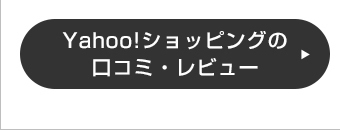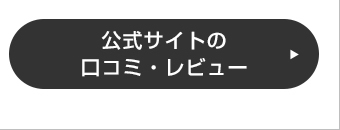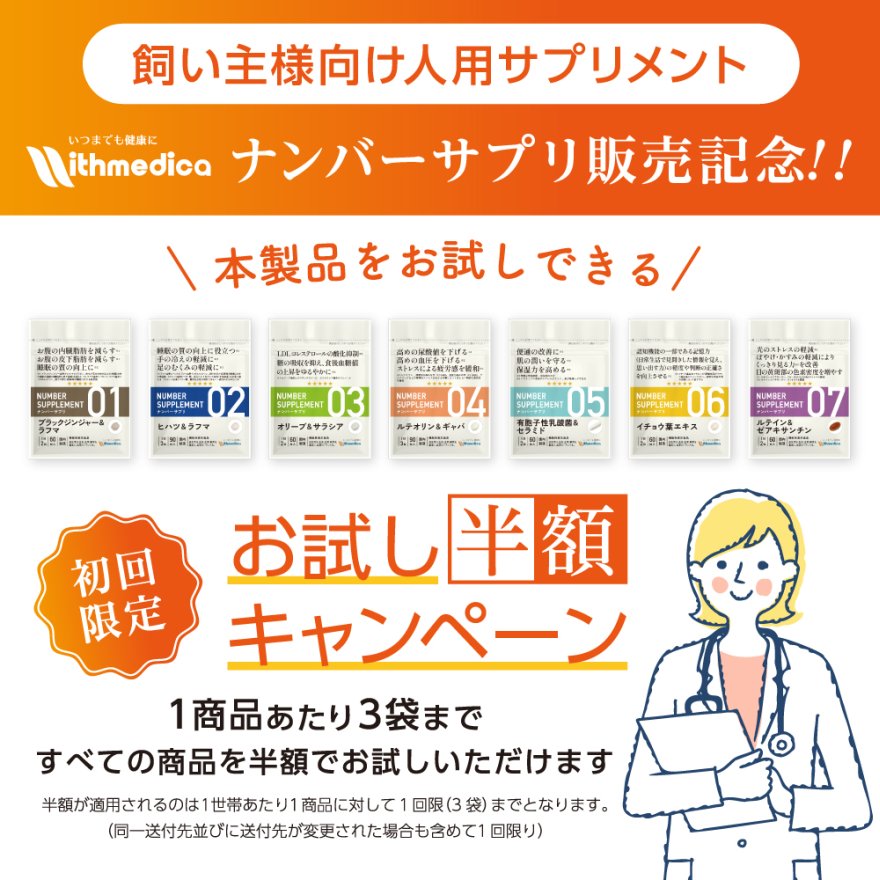犬の東洋眼虫症とは
東洋眼虫が結膜嚢内に寄生します。
東洋眼虫は、結膜嚢内にて生活する5~18mm程度の寄生虫です。東洋眼虫症は、西日本で多く見られる感染症で、ショウジョウバエの1種であるメマトイが媒介します。
犬の東洋眼虫症の症状とは
結膜や角膜など、眼の表面に症状がみられます。
東洋眼虫症の犬は、臨床症状に乏しいとされていますが、ときに大量の粘液膿性の眼脂を伴う流涙症、急性の結膜炎、濾胞性結膜炎、結膜浮腫、角膜炎、眼瞼痙攣が見られることがあります。また、眼をこすりつけるなど、眼の不快な症状を示すこともあります。
目視で成虫の虫体を観察することができますが、少数の寄生では見落としやすいため、点眼麻酔を施した後、結膜嚢内、とくに第三眼瞼を反転させて観察をしっかりすることが重要です。
東洋眼虫の最終宿主は犬、タヌキ、キツネなどのイヌ科の動物の他、猫、牛などが挙げられます。また、異常宿主として人間が挙げられ、人獣共通感染症が懸念される疾患です。
犬の東洋眼虫症の原因とは
東洋眼虫が原因となります。
眼虫感染症を引き起こす寄生虫は、Thelazia callipaeda、T.Californiensis、T.gulosaなどが挙げられますが、日本で見られる眼虫は主にT.callipaedaで、いわゆる東洋眼虫のことです。
東洋眼虫の成虫は、宿主の眼球内ではなく結膜嚢内にて生活し、雌雄がいると卵胎生で繁殖します。日本での中間宿主は、メマトイ類と呼ばれる、涙液分泌物を摂食するショウジョウバエの1種になります。涙液分泌物を摂食すると同時にL1幼虫が中間宿主に感染し、薬1か月でメマトイの体内でL3幼虫となり、再び最終宿主となる動物での涙液摂食時に感染機会をうかがいます。
東洋眼虫は、1910年にパキスタン国内の犬で初の報告があって以降、感染地域はアジアを中心としたものでしたが、近年はヨーロッパにまで感染地域が拡大しているとされています。
日本では1957年に宮崎県で犬と猫の感染例が報告されて以来、西日本に多い寄生虫であるとされていますが、1978年に神奈川県の犬での寄生が報告されて以降、日本全国で感染の報告があります。
犬の東洋眼虫症の好発品種について
全犬種で好発します。
東洋眼虫症は寄生虫による感染症であるため、どの犬種にも見られる可能性があります。屋外飼育している場合は、リスクが高くなります。
犬の東洋眼虫症の予防方法について
フィラリア予防をおこなうことが東洋眼虫の予防につながります。
東洋眼虫症の治療には、フィラリア症予防に用いられる抗線虫薬の効果が認められています。そのため、フィラリア症の予防薬を投与することが、東洋眼虫症の予防にもつながると言えます。ただし、抗線虫薬は、効果が得られるまで1~2週間が必要なこと、完全には駆虫出来ない場合があること、など注意が必要です。
また、屋外飼育している場合はリスクが高くなるため、東洋眼虫症の予防には屋内飼育が効果的と言えます。
犬の東洋眼虫症の治療方法について
用手法にて除去します。
東洋眼虫を発見したら、まずは用手法にて除去をおこないます。
点眼麻酔を複数回点眼します。性格が荒い場合は、必要に応じて鎮静や全身麻酔を施します。虫体をピンセットや綿棒で摘出しますが、その際に第三眼瞼の裏側に虫体が隠れている場合もあるため注意が必要です。虫体を摘出したら、生理食塩水にて勢いよく虫体を洗い流すように結膜嚢内の洗浄をおこないます。その後消炎剤の点眼液を数日投与します。
抗線虫薬の投与
ミルベマイシンオキシムの内服、モキシデクチンの皮下への滴下などで効率的に駆虫することが出来ます。ただし、駆虫までに1週間程度必要なこと、完全に駆虫できない場合があること、などの問題もあるため、まずは虫体を摘出することが推奨されます。あくまで補助的な治療法であると考えたほうが良いかもしれません。
完全に虫体が駆虫されたら、再感染しない限り眼の症状は速やかに改善します。屋外飼育している場合は再感染のリスクがあるため注意が必要です。