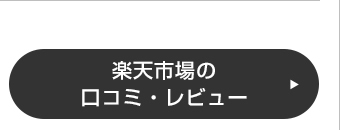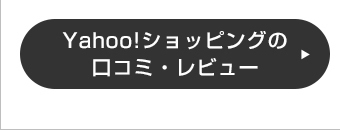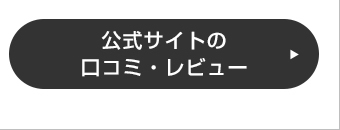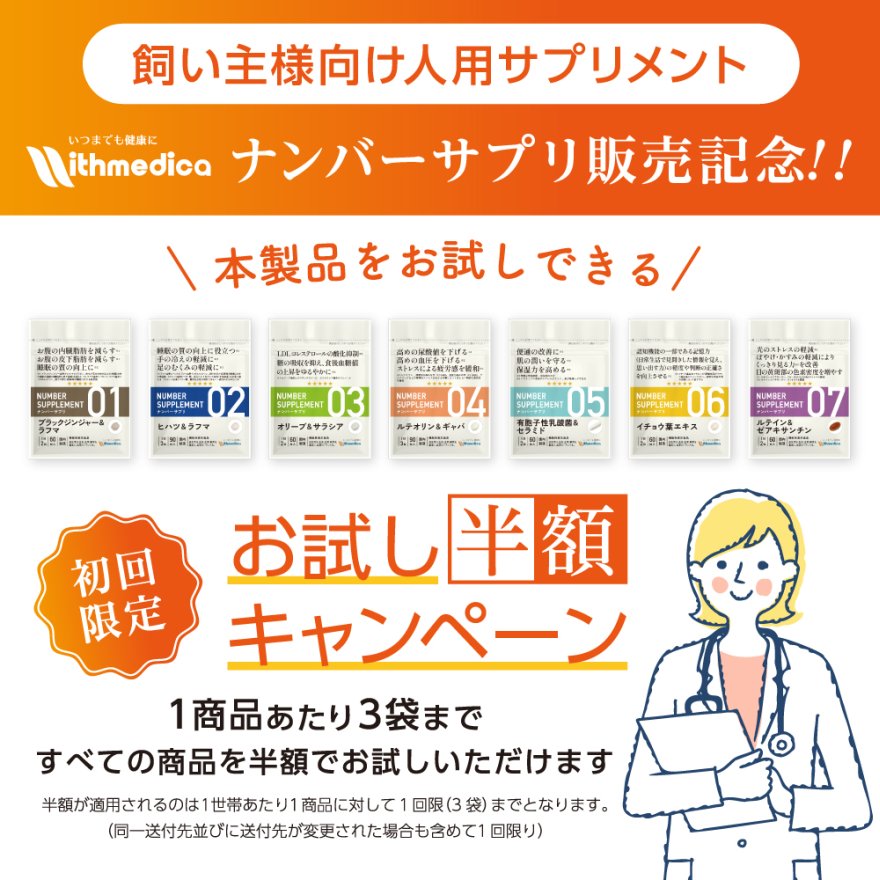猫の皮膚糸状菌症とは
真菌の感染による皮膚炎です。
皮膚糸状菌症は、真菌の中でも菌糸を伸ばして増殖する糸状菌によって引き起こされる皮膚炎です。
様々な哺乳動物で見られる病気で、人にも感染するため、人獣共通感染症として問題となる病気です。
猫では糸状菌は被毛や皮膚に付着し、菌糸を伸ばしながら増殖して、脱毛や赤み、フケ、痂皮形成などの皮膚病変を起こします。
接触感染によってヒトや他の同居動物にうつります。
多頭飼育の場合や若齢の猫で発症することが多いですが、背景に基礎疾患が潜んでいるために発症することもあります。
その場合には全身的な健康診断を行い、基礎疾患を治療しなければ、なかなか皮膚症状が改善しない、良くなってもすぐに再発するという事態になってしまいます。
猫の皮膚糸状菌症の症状とは
円形の脱毛を主とした皮膚症状がみられます。
皮膚糸状菌症の主な症状は以下の通りです。
・円形の脱毛
・脱毛部分の辺縁の皮膚がめくれる
・痂皮形成
・脱毛部分の発赤
・水疱形成
・フケが増える
・皮膚にしこりができる
・痒み
皮膚糸状菌症では痒みの症状が出ますが、他の寄生虫感染などによる皮膚疾患と比べるとその程度は軽度であることが多いようです。
一方、糸状菌が人に感染した場合は、非常に強い痒みを引き起こします。
症状は全身どこにでも出ますが、猫では顔、手足、尻尾に病変ができやすい傾向があります。
病変部の皮膚や被毛を検査し、真菌の分生子といわれる特徴的な構造や菌糸を検出する、あるいは被毛を一部検査用の培地で培養することで、皮膚糸状菌症の診断を行います。
猫の皮膚糸状菌症の原因とは
接触感染します。
皮膚糸状菌に感染している動物からの接触感染によっておこります。
そのため、多頭飼育環境下に入り込むと次々に感染が拡大し、大きな問題となります。
その他には、自然界の土や、糸状菌に感染した被毛を含む埃などからの感染もあります。
免疫力の低下などによって起こります。
多くの皮膚糸状菌症は、健康な動物であれば発症しても自然治癒します。
しかし、免疫力が十分でない子猫や、何らかの基礎疾患を持つ猫、他の病気の治療のために高用量のステロイドや免疫抑制剤などを服用している場合には、発症した後自力で回復できず、悪化してしまうケースがよく見られます。
猫の皮膚糸状菌症の好発品種について
以下の猫種で好発がみられます。
- ペルシャ
ペルシャ以外でも、1歳以下の若い子猫や長毛種、免疫力の低下している猫で発症しやすい傾向があります。
猫の皮膚糸状菌症の予防方法について
感染猫との接触を断つために室内で飼育しましょう。
外に出ると、どうしても不特定多数の猫や汚染された土壌などとの接触機会が増えてしまいます。
室内飼育を徹底し、感染している外猫と接触できないようにすることで、ある程度感染を予防できます。
衛生的な環境下で生活できるようにしましょう。
生活環境を整備することはとても重要です。
定期的に掃除機で部屋を掃除し、ケージやトイレ、食器なども不衛生にならないよう、こまめに消毒薬で拭いたり、洗浄するように心がけましょう。
糸状菌の消毒には塩素系の消毒剤が有効です。
猫の皮膚糸状菌症の治療方法について
限局的な感染の場合は外用療法で治療します。
多くの糸状菌症は自然に改善することが多いのですが、回復までにはある程度長期間がかかるため、その間に同居している他の動物やヒトにもうつしてしまうことが懸念されます。
適切に治療を行えばその期間を短縮し、リスクを軽減できます。
皮膚病変が限局的な場合は、シャンプーや外用薬での治療を行います。
周囲を少し広めに毛刈りして真菌に感染している被毛を取り除き、抗真菌剤を含むシャンプーで洗浄します。
その後、抗真菌剤を含む外用薬を塗り込みます。
外用薬の塗布後は、猫が自分で薬をなめとってしまわないように、薬が浸透するまでしばらくはエリザベスカラーなどで保護しましょう。
全身性に症状がみられる場合は内服薬が必要です。
皮膚病変が多発している場合や広範囲に及ぶ場合には、上記の治療に加えて内服薬で抗真菌剤を投与します。
抗真菌剤の投与中は、吐き気や下痢などの消化器症状や肝臓への負担など、副作用がみられることがあるため、体調には十分注意し、定期的に血液検査をすることが必要です。
また、投与は数週間から数カ月継続する必要があり、治療には長期間を要します。
中途半端に投薬をやめてしまうと、再発することが多いため、指示された投与期間を守ってしっかり治療しましょう。
治療とともに環境整備を行います。
生活環境に糸状菌が残っていると再感染の原因となります。
治療期間中はこまめに掃除をし、脱落した被毛やフケが環境中に残らないように心がけましょう。
また、ベッドなども消毒するか、新しいものに交換し、感染源を残さないようにしましょう。
皮膚病変のある猫を触った後は、手洗いを念入りにし、多頭飼育の場合には治療がひと段落するまで他の猫と隔離して生活させることが必要です。