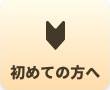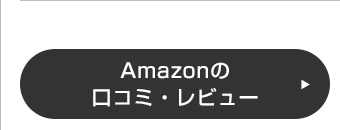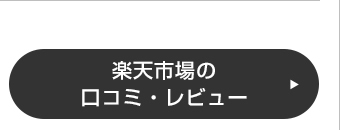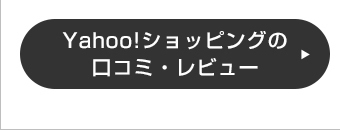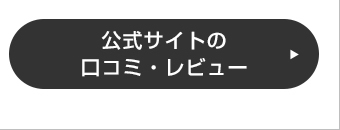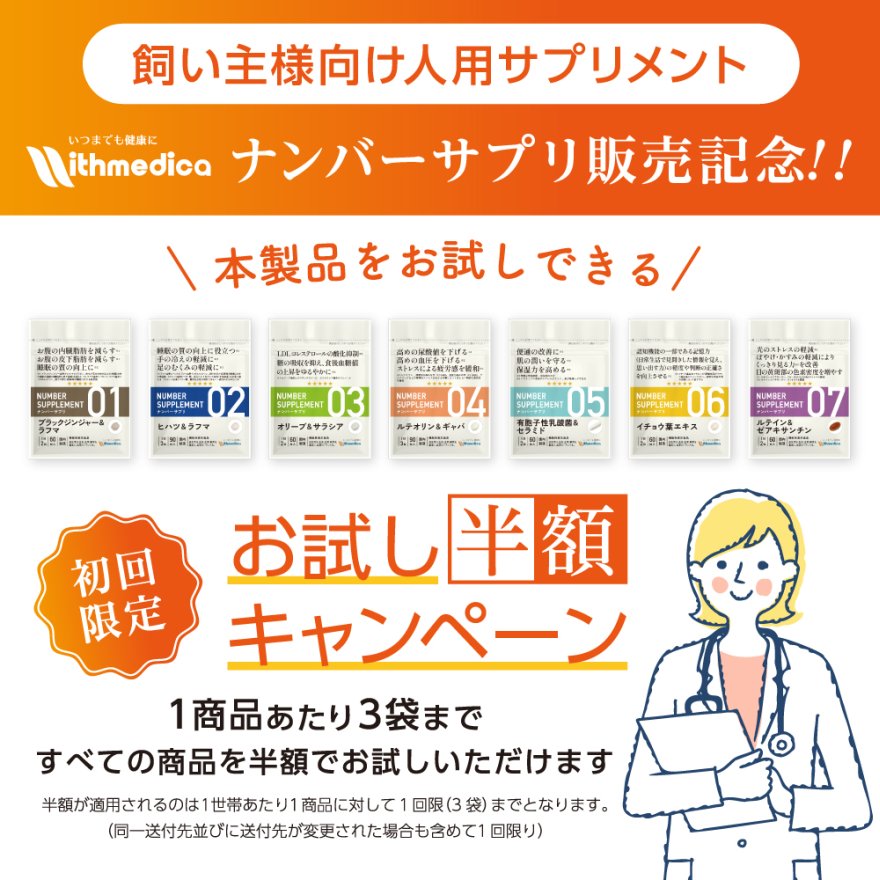犬コロナウイルス感染症とは
犬コロナウイルスの感染によって引き起こされる感染症です。
犬コロナウイルス感染症は、犬コロナウイルスの感染によって下痢や嘔吐を引き起こすウイルス性の腸炎です。犬パルボウイルスと混合感染することが多く、その場合は症状が重くなります。
犬コロナウイルス感染症の症状とは
消化器症状が認められます。
犬コロナウイルス感染症は、食欲不振、嘔吐、水様性下痢、脱水といった消化器症状を示します。致死的な転機は、ほとんどの場合が犬パルボウイルス感染症、犬アデノウイルスⅠ型感染症、犬ジステンパーウイルス感染症との併発によるものであるとされています。犬パルボウイルス感染症とは異なり、白血球数の減少は認められません。
犬コロナウイルス感染症の診断には、臨床症状に加え、抗体検査およびPCR検査により検出が可能です。
犬コロナウイルス感染症の原因とは
犬コロナウイルスが経口感染します。
犬コロナウイルス感染症は、コロナウイルス科コロナウイルス属に属する犬コロナウイルスを原因としますが、猫の猫伝染性腹膜炎やヒトの新型コロナウイルス感染症とは別のウイルスになります。
犬コロナウイルス感染症は、軽度な胃腸炎を引き起こす自己制御感染症の病因因子とされていましたが、仔犬の場合には死亡するような高病原性のコロナウイルスにも変異するとされています。高い感染率を有しますが、一般的には致死率が低いことを特徴とします。高力価ウイルスは糞便中へと排出され、経口摂取により感染します。通常は消化管に限局して感染します。
犬コロナウイルス感染症の好発品種について
全犬種で好発します。
犬コロナウイルス感染症は、感染症であるためどの犬種でも発症する可能性があります。仔犬、免疫抑制剤を投薬している、ワクチンの接種をしていない、などの免疫の低下した状態ではリスクが高まることに注意が必要です。
犬コロナウイルス感染症の予防方法について
予防にはワクチン接種は有効です。
犬コロナウイルス感染症は、ワクチンがあるため接種することで予防効果が期待できます。ワクチンの製品によって多少違いはありますが、6週齢以上9週齢未満の場合は3週間隔で3回で接種し、9週齢以上12週齢未満の場合は3週間隔で2回接種します。それ以降の再接種は個々の獣医師の判断に委ねられています。
犬においては、ワクチン接種後に免疫介在性および非免疫介在性のメカニズムにより、限局性または全身性の有害事象が発生することがあります。ワクチン接種後有害事象が発生した場合には適切な対処が必要となるため、必ず動物病院に速やかに相談しましょう。
また、飼育環境や衛生管理を向上させることも大切です。
犬コロナウイルス感染症の治療方法について
支持療法が中心となります。
犬コロナウイルス感染症に特異的な治療方法があるわけではないため、支持療法が中心となります。
脱水をともなっている場合には、乳酸リンゲル液などで脱水を改善させます。脱水が改善されれば、グルコースを含んだ輸液剤で維持量とする輸液療法を開始します。CBC、総蛋白濃度、血糖値および電解質濃度をモニターします。必要であれば塩化カリウムを追加し、低カリウム血症の補正をおこないます。低血糖に対しては、グルコースを含んだ輸液剤にて補正をおこないます。
頻回の嘔吐による体液喪失、電解質喪失、誤嚥性肺炎、食道炎の予防目的も含め、制吐薬としてメトクロプラミド、マロピタントなどの投与をおこないます。メトクロプラミドを選択する際は、腸重積の有無に注意する必要があります。
嘔吐があっても絶食はおこなわず、なるべく早い段階(24~72時間)から少量の給与を開始し、徐々に食事量を増やしていきます。