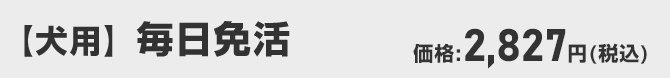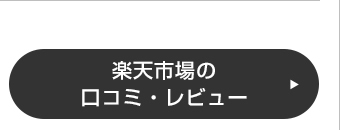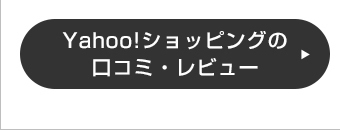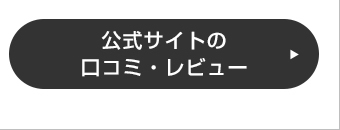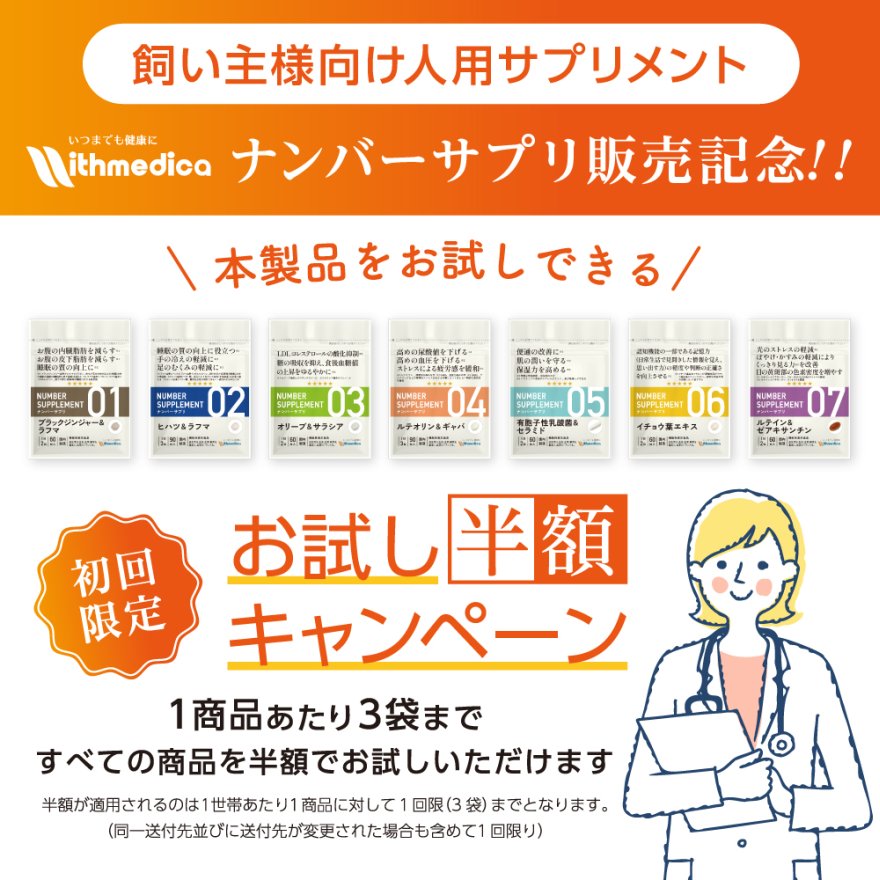犬のGIST(消化管間質腫瘍)とは
消化管筋層内にあるカハール介在細胞が腫瘍化したものです。
消化管間質腫瘍とは、消化管筋層内にあり蠕動運動に関連したペースメーカーとして働く、カハール介在細胞が腫瘍化したものを言います。
犬のGIST(消化管間質腫瘍)の症状とは
巨大化することで腹囲膨満が認められます。
消化管間質腫瘍は臨床症状は認めず健康診断で偶発的に確認されることも多いですが、巨大化による腹囲膨満の他、消化管出血による重度の貧血や消化管穿孔による細菌性腹膜炎を認めることもあります。
身体検査の後に全身状態や麻酔リスクの評価のための完全血球計算・血液化学検査・血液凝固線溶検査、転移徴候や麻酔リスク評価のための胸部X線検査、そし腹部超音波検査をおこないます。腹部超音波検査では、病変の発生部位や転移・播種徴候の有無の他、腹水の有無を確認し、腹水がある場合は必ず穿刺採取して細菌性腹膜炎の有無を評価します。
腫瘍が概して巨大化するため、腹部超音波検査で発生部位や全体像が把握できない場合はCT検査が有用です。ただし、管外発育型の場合、発生部位との接着がわずかで、かつ巨大化しているため他の腹腔内臓器とも接しており、発生部位がわからないこともあります。
犬のGIST(消化管間質腫瘍)の原因とは
カハール介在細胞が腫瘍化したものです。
消化管間質腫瘍とは、消化管筋層内にあり蠕動運動に関連したペースメーカーとして働く、カハール介在細胞が腫瘍化したもので、c-kit遺伝子の変異が腫瘍化に関与しています。
発生部位は粘膜下で、細胞形態は同部位から発生し得る平滑筋や抹消神経由来の腫瘍とも類似していますが、消化管筋層内にある正常細胞の中でカハール介在細胞のみが発現しているKIT蛋白(CD117)またはCD34(血管内皮や幼弱な造血幹細胞と共通する表面抗原)が染色されるかで鑑別します。
犬のGIST(消化管間質腫瘍)の好発品種について
全犬種で好発します。
発生年齢中央値は10歳前後と考えられ、性差や犬種にいよる偏りはないとされています。
犬のGIST(消化管間質腫瘍)の予防方法について
早期発見、早期治療をおこないます。
消化管間質腫瘍は予防は難しい疾患ですが、臨床症状を伴う前に早期に発見できれな手術リスクが低くなるため、超音波検査をはじめとした定期的な画像診断が有用です。
犬のGIST(消化管間質腫瘍)の治療方法について
外科的切除
消化管間質腫瘍の治療の原則は外科的切除になります。巨大化するため一見外科不適応と思われがちですが、膜構造を含めた解剖学的知識と癒着を剥離する技術があれば多くの場合切除可能です。一見巨大で切除困難と予想されるものでも丹念に癒着を処理すれば、発生部位は狭小であることも少なからずあると言われています。
他の悪性腫瘍性疾患と同様に十分な側方マージン(3~6cm)を確保して切除するのが原則ですが、胃幽門部付近や十二指腸の膵管や胆管に近接して発生し十分なマージンを確保すると術後合併症リスクが高くなる場合は、核手術(腫瘍のみをくり抜くように切除すること)も有用と言われています。
内科療法
消化管間質腫瘍に対して奏効する殺細胞性抗がん薬はないものの、消化管間質腫瘍は受容体型チロシンキナーゼ(KIT)をコードするc-kit遺伝子変異を認めることが多いため、c-kit変異に対するチロシンキナーゼ阻害薬であるイマニチブが奏効することがあります。
予後
犬の消化管間質腫瘍は原則として外科的切除をはじめとした治療後の生存期間中央値は比較的長期で、900日以上と考えられています。肝臓をはじめとした腹腔内転移や播種を後に認めた例でも、イマニチブをはじめとした分子標的薬の併用によってその後長期生存することも多いとされています。腹腔内播種や肝転移は一般的ですが、肺転移は比較的まれとされています。ただし、核分裂が多い症例をはじめとして、一部の症例では非常に短期の経過をたどることがあるので注意は必要です。