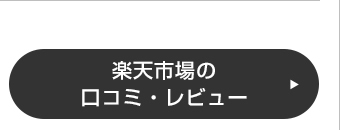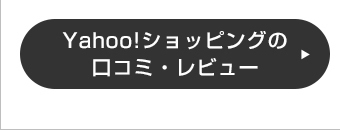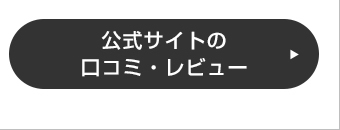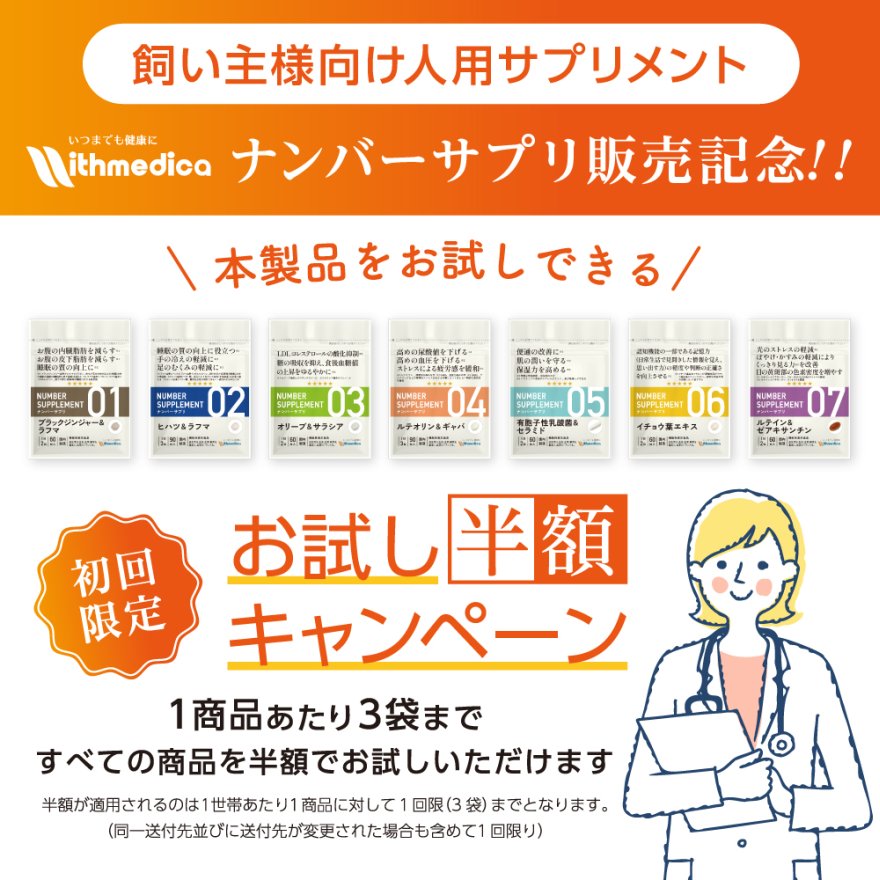犬の炎症性腸疾患(IBD)とは
犬で慢性の消化器症状を引き起こす原因不明の疾患です。
対症療法に効果を示さない、または再発を繰り返す慢性の消化器症状を示す病態を慢性腸症と呼びます。慢性腸症は治療反応性により、食事反応性腸症、抗菌薬反応性腸症、炎症性腸疾患に分類されます。炎症性腸疾患は免疫抑制薬に治療反応を示すことから、免疫抑制薬反応性腸症と呼ばれることもあります。炎症性腸疾患は、原因特定が出来ず、腸に慢性的な炎症が見られます。
犬の炎症性腸疾患(IBD)の症状とは
慢性の消化器症状を引き起こします。
主な症状としましては、小腸性下痢、大腸性下痢、嘔吐、体重減少、腹痛などが認められます。上部消化管(食道、胃、十二指腸)の病変が重度である場合は嘔吐や小腸性下痢がよく見られ、大腸の病変が重度である場合は大腸性下痢がよく見られます。
小腸性下痢は、軟便から水様便など様々ですが、便の量が増え、回数はそれほど増えない傾向があります。小腸に出血がある場合は黒色便が見られます。大腸性下痢は、軟便、粘液便、血便がよく見られ、便の回数が増える傾向があります。
炎症性腸疾患は、炎症が起こっている細胞の種類や部位によって、リンパ球プラズマ細胞性腸炎、好酸球性胃腸炎、肉芽腫性腸炎、組織球性潰瘍性腸炎などに分類されます。
バセンジーの免疫増殖性腸炎
バセンジーで見られる遺伝的な炎症性腸疾患とされています。小腸性下痢や嘔吐が見られ、ストレスで悪化することがあります。予後は数年とされており、重度な炎症性腸疾患と言えます。
ボクサーの組織球性潰瘍性結腸炎
主に若齢のボクサーやフレンチブルドッグに見られる炎症性腸疾患です。大腸に潰瘍が形成され、下痢、血便、しぶりなどが見られ、重度になると体重減少や食欲不振を引き起こします。炎症性腸疾患の中では、治療反応性が低く、予後が悪いとされています。
犬の炎症性腸疾患(IBD)の原因とは
原因が不明な疾患です。
炎症性腸疾患は、一般的な検査で原因特定出来ない消化器疾患と定義されています。
腸粘膜における持続的な炎症、腸絨毛の障害によって消化器症状が見られます。持続的な炎症は、腸粘膜の過剰な免疫応答、腸粘膜バリアの異常、腸内細菌叢の異常などの複数の因子がかかわっていると考えられています。
犬の炎症性腸疾患(IBD)の好発品種について
以下の犬種で好発がみられます。
- シャーペイ
- ジャーマンシェパード
- バセンジー
- フレンチブルドッグ
- ボクサー
リンパ球プラズマ細胞性腸炎では、ジャーマン・シェパード、チャイニーズ・シャーペイなどの犬種で発生率が高いとされ、免疫増殖性腸炎ではバセンジー、組織球性潰瘍性結腸炎ではボクサー、フレンチ・ブルドックが好発犬種です。
犬の炎症性腸疾患(IBD)の予防方法について
主に早期発見・早期治療をおこないます。
予防方法はありません。早期発見・早期治療をおこないます。
犬の炎症性腸疾患(IBD)の治療方法について
免疫抑制剤を用いた治療をおこないます。
食事反応性腸症、抗菌薬反応性腸症が除外され、腸粘膜に炎症が認められた場合、免疫抑制剤の投与をおこないます。免疫抑制剤の第1選択はステロイド剤となりますが、ステロイド剤の効果が不充分である場合やステロイド剤の量を減量したい場合は、他の免疫抑制剤を併用することがあります。
腸粘膜にリンパ管拡張所見が認められる場合は低脂肪の療法食を投薬治療と並行して用いることもあります。低脂肪療法食で効果が不充分である場合は、ササミ、ジャガイモ、白米などを用いた超低脂肪の手作りごはんの使用を検討します。
下痢の改善のため、免疫抑制剤に併用して抗菌薬を投与することがあります。大腸性下痢が主体となる場合、可溶性食物繊維の投与を検討します。
ステロイド剤の単独投与や他の免疫抑制剤との併用によって良好にコントロールが出来ることが多いため、予後は悪くないと言えます。しかし、多くの症例で何らかの薬剤の投与が必要になります。