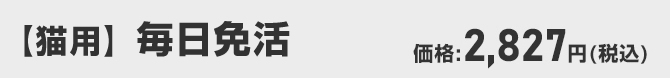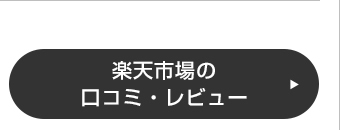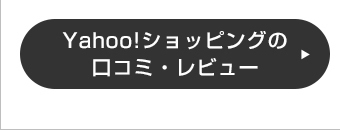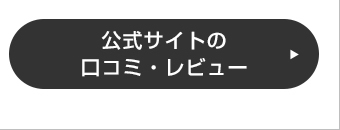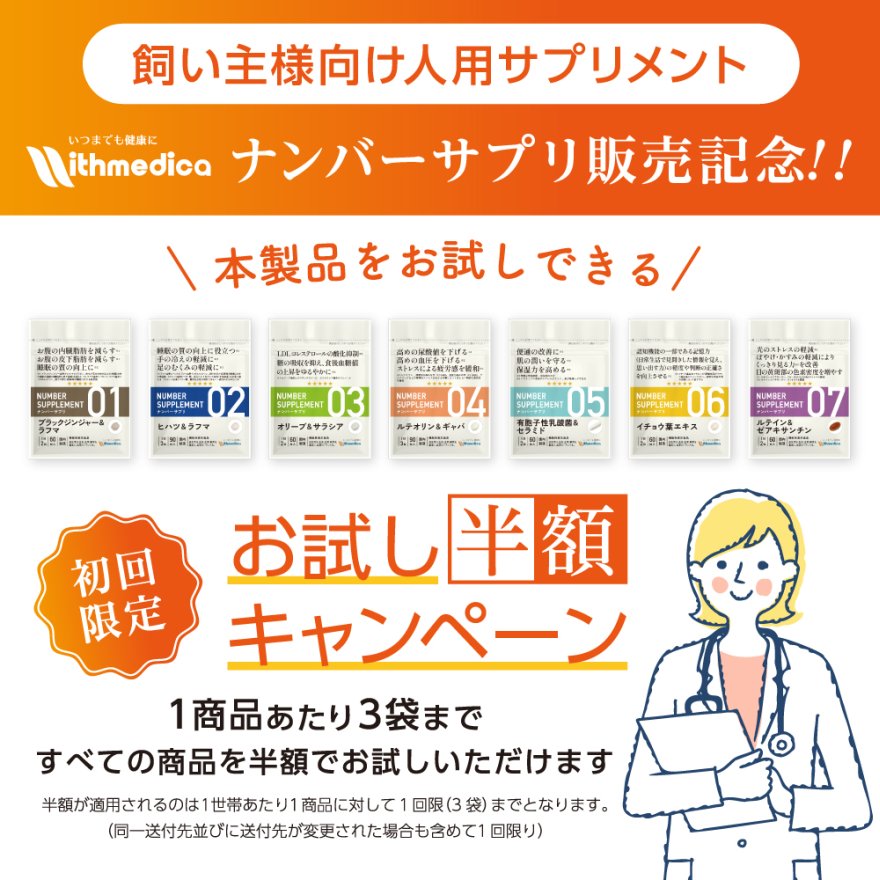猫の肥満細胞腫とは
皮膚や臓器に病変を作る腫瘍です。
肥満細胞とは、免疫に関わる細胞の一種です。
主に皮膚や粘膜面近くに分布しており、体に侵入してくるアレルギー性物質などに対して炎症反応を起こし、体を守る役割の一端を担っています。
この肥満細胞が皮膚や臓器で異常増殖し、病変を作ってしまうことがあります。
これを肥満細胞腫といいます。
猫では皮膚や脾臓、肝臓、腸管などに病変を作ることが多く、皮膚にできる場合と内臓に発生する場合は同程度とされています。
肥満細胞腫は一般的に悪性腫瘍に分類されますが、発生部位によってその挙動が異なり、予後が全く異なります。
皮膚の肥満細胞腫は比較的緩やかに進行し、外科切除単独で良好な予後が得られることが多いですが、腸管に発生した肥満細胞腫は進行が速く転移も高率に起こり、予後が悪いとされています。
肥満細胞腫は細胞や臨床症状に特徴があるため、比較的診断がつきやすい腫瘍ですが、内臓にできるタイプの肥満細胞腫では発見が遅れてしまうこともあります。
皮膚にしこりを見つけた場合や、元気・食欲がない、頻繁に吐くなどといった症状が見られた場合にはできるだけ早く病院を受診しましょう。
猫の肥満細胞腫の症状とは
皮膚肥満細胞腫は皮膚にしこりを作ります。
猫の皮膚腫瘍の中で、肥満細胞腫は2番目に多いとされています。
肥満細胞腫はどこにでもできますが、猫の皮膚では頭頚部に好発し、特に眼の周囲と耳にしこりを形成することが多い腫瘍です。
皮膚に粒状~ドーム状の膨らみを形成し、その部分の毛が抜けることもあり、しこりを触った後には一過性に熱を持って腫れたようになることがありますが、しばらくすると元に戻るのが特徴です。
肥満細胞腫は炎症細胞の一種で、アレルゲンなどに反応して細胞内に持っている顆粒からヒスタミンという物質を放出して炎症反応を起こす細胞です。(脱顆粒)
しこりを機械的に刺激すると脱顆粒が起こり、一過性の赤みや腫れなどの炎症反応を起こすのです。
腫瘍は徐々に大きく成長していきますが、その速度は比較的ゆっくりです。
多くの場合は単発性で良性の経過をたどることが多いですが、中には複数個所に多発することもあり、多発するタイプでは内臓への転移が起こっている場合もあるため、注意が必要です。
内臓型肥満細胞腫は脾臓や肝臓に好発します。
肥満細胞は免疫細胞の一種なので、全身のどこにでも存在します。
そのため、脾臓や肝臓、消化管などの内臓にも病変を形成することがあります。
内臓型の肥満細胞腫は目に見える部分に腫瘤を形成しないため、診断までに時間がかかることがあります。
症状としてよく認められるものは
・食欲不振
・元気がない
・嘔吐することが多い
・下痢
・黒色便
・貧血
などです。
これらの症状は他のさまざまな疾患でも見られる症状のため、血液検査・レントゲン検査・超音波検査などを一通り行い、場合によっては病変部(臓器)に針を刺して組織を検査する針生検を実施して診断します。
中でも脾臓は好発する臓器で、肥満細胞腫になると脾臓が大きく腫れ(脾腫)、お腹の触診でも内臓が腫れているのがわかる場合があり、続いて肝臓などにも転移します。
消化管にできる肥満細胞腫では、進行すると消化管が閉塞してしまうことがあり、その場合には嘔吐が非常に強く見られます。
また、消化管の閉塞とは別の理由でも高率に消化器症状が現れます。
内臓型の肥満細胞腫では、肥満細胞が持つ顆粒からヒスタミンが放出され、持続的な高ヒスタミン血症を起こします。
このヒスタミンによって胃酸の分泌が過剰になると、胃や十二指腸に潰瘍が形成され、吐き気や嘔吐、下痢、黒色便などがみられます。
猫の肥満細胞腫の原因とは
原因不明です。
肥満細胞腫がどのような原因で発生するのかはわかっていません。
猫の肥満細胞腫の好発品種について
以下の猫種で好発がみられます。
- シャム
皮膚の肥満細胞腫はシャム猫で好発傾向が認められます。
その他の肥満細胞腫には、品種による好発傾向はありません。
猫の肥満細胞腫の予防方法について
効果的な予防方法はありません。
原因がわかっていないため、効果的に予防する方法は現在のところありません。
猫の肥満細胞腫の治療方法について
皮膚肥満細胞腫は外科切除します。
皮膚の肥満細胞腫の治療は、外科的な切除が第一選択です。
形成された腫瘤が一か所のみで、腫瘍が小さい内に腫瘍の周囲を十分に広く切除した場合には予後は良好です。
腫瘍が大きく成長してしまっている場合には、腫瘍の周囲に浸潤した腫瘍細胞が手術によって取り切れず、再発することがあります。
また、小さな病変でも多発している場合には、すべての病変部を切除し、ステロイド剤や抗がん剤、分子標的薬というお薬で補助的な内科治療を行う場合もあります。
脾臓の肥満細胞腫では脾臓摘出を行います。
脾臓の肥満細胞腫で転移が起こっていない場合には、外科手術(脾臓の摘出)だけでも予後は比較的良好です。
肝臓やリンパ節に転移が起こっている場合や、肥満細胞が血液中にたくさん認められる場合には、術後に補助療法として抗がん剤やステロイド剤、分子標的薬などで腫瘍細胞を抑える治療を行っていきます。
腸管の肥満細胞腫はあまり予後が良くありません。
腸管の肥満細胞腫もまた同様に外科手術が治療の第一選択肢となりますが、上記の2つのタイプとは異なり、予後があまり良くありません。
多くの場合、診断時にリンパ節や脾臓、肝臓に転移が起こっており、しこりを含めて大きく(長く)腸管を切除し、抗がん剤治療やステロイド、分子標的薬で治療を行っても、術後数カ月で全身状態が悪化して亡くなる場合が多いタイプです。
支持療法で消化器症状を抑えます。
内臓型の肥満細胞腫では、肥満細胞から放出されるヒスタミンによって持続的な高ヒスタミン血症となっており、嘔吐の頻度が多く食欲も低下します。
そのため、肥満細胞腫と診断された場合にはヒスタミンの作用を抑える抗ヒスタミン剤や胃粘膜保護剤、ステロイド剤などを投与し、消化管粘膜を保護する必要があります。
また、抗がん剤や分子標的薬を使用した場合には、副作用としても吐き気や下痢、食欲不振などの症状が現れることがあります。
その場合には適宜点滴などを行って体調を整える治療を行います。