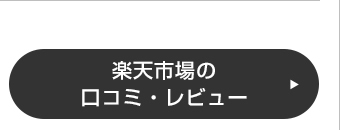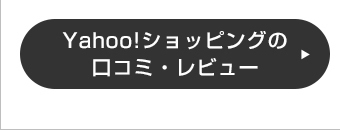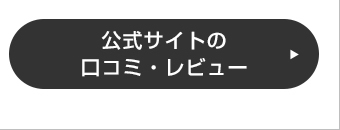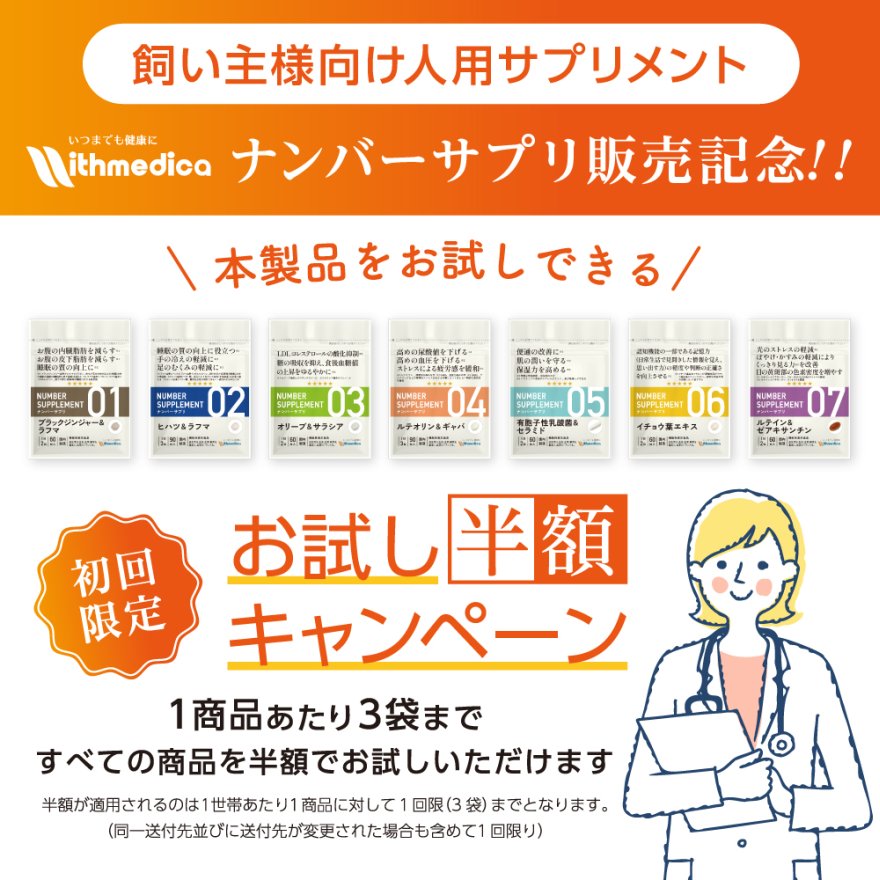犬の動脈管開存症とは
胎児期の血管が残存することによる心臓病です。
犬の先天性疾患でよくみられるものの一つです。胎児期に心臓にあり、出生後閉鎖する血管(動脈管)が開存することで、心肺の機能障害を引き起こします。初期は症状はありませんが、徐々にすぐ疲れる、散歩にいきたがらない、咳が出やすい、呼吸が浅く速いなどの症状がみられるようになります。
強く症状がでる場合は外科的な処置も視野に入れた積極的な治療を行います。おおむね、治療の反応性がよい病気ですが、病状が悪化している場合、外科的な処置が選択できないこともあります。
犬の動脈管開存症の症状とは
運動不耐性、呼吸器症状がみられます。
初期の動脈管開存症では無症状であることが多く、うっ血性心不全が続発することで運動不耐性や呼吸困難などの症状が出るようになります。
うっ血性心不全は、全身に流れるはずの大動脈血が一部、肺を通じて心臓に戻ってきてしまうことにより、肺から血流を受ける左心房と、左心房の血流を全身に送り出す左心室の負荷が増大し、心房室が拡大することで引き起こされます。左心房室の拡大は僧帽弁閉鎖不全などの原因になり、併発することで病状が悪化します。
持続的な肺への血流の増大は、肺高血圧を通じて肺水腫を起こし、咳や頻回の浅い呼吸、チアノーゼなどの症状を引き起こします。病状が進行し、肺の血圧が動脈血より高くなることで、初期の動脈管開存症で動脈管を通じて大動脈→肺動脈に流れていた血流が、肺動脈→大動脈に逆流するアイゼンメイジャー症候群と呼ばれる状態になります。
アイゼンメイジャー症候群を併発した動脈管開存症では、上半身の粘膜色(口腔や眼瞼)は正常で、下半身の粘膜色(膣や肛門)が青白いという特徴的な症状がみられます。このタイプの動脈管開存症では手術が禁忌となり、また予後が良くありません。
犬の動脈管開存症の原因とは
胎児期の血管である動脈管の開存が原因になります。
胎児期の犬は酸素を母親から供給されるため肺に血流を送る必要がありません。そのため肺動脈(肺に向かう血管)と大動脈(全身に血液を送る血管)をバイパスする血管が発達しており、動脈管と呼ばれます。動脈管は生後数日で閉鎖されますが、動脈管開存症では成長した犬で動脈管が機能している状態になります。
生後に動脈管が機能していることで、大動脈に流れる全身に向かう血液の一部が肺動脈に流れ込み、肺と心臓に負荷をかけ、うっ血性心不全や肺高血圧症などを引き起こします。
犬の動脈管開存症の好発品種について
以下の犬種で好発がみられます。
- シェットランドシープドッグ
- チワワ
- ポメラニアン
- マルチーズ
- ミニチュアダックスフント
チワワ、トイ・プードル、ミニチュア・ダックスフンド、マルチーズ、ポメラニアン、コリー、シェットランド・シープドックなどが好発犬種であると言われており、雌で特に発症率が高い疾患です。
犬の動脈管開存症の予防方法について
早期発見、治療をおこないます。
動脈管開存症は先天性疾患であり、予防方法はありません。症状の早期発見・治療が重要になります。心雑音の聴診などで比較的早期発見がしやすい疾患であるため、犬を飼い始めたら定期的に病院に連れていき、成犬になってからは健康診断を受けることが非常に有効です。
犬の動脈管開存症の治療方法について
主に外科的な手術を行い治療します。
アイゼンメイジャー症候群を併発していない動脈管開存症では、外科手術により根治、または症状の大幅な改善を期待できます。動脈管を外科的に閉鎖するには血管を外側から結紮する、血管を内側からコイル等で塞ぐなどの方法があります。前者は古典的な方法であり、後者は比較的新しい方法です。
外科療法は早期に実施するべきですが、小さな子犬には負担が大きいため、内科的な治療を行いながらある程度の成長を待つ場合があります。ACE阻害薬や利尿薬などの心肺の負担を軽減する薬を使用します。
アイゼンメイジャー症候群を併発している場合、手術を行うことはできません。このタイプの動脈管開存症では、大動脈圧よりも肺動脈圧が高くなっており動脈管を通じて肺動脈→大動脈に血流が流れています。つまり、かなり高血圧になってしまっている肺動脈の圧力を大動脈に逃がしていることになります。この状態で動脈管を閉鎖すると、肺動脈の圧力が急激に上昇し、重篤な肺水腫を引き起こし死に至ることがあります。
アイゼンメンジャー症候群になってしまっている場合は、肺高血圧症と多血症の管理を行います。肺高血圧症は内服薬を、多血症は血液を薄めるために定期的に瀉血を行います。